大学生でも新NISAを始める人が増えている理由
新NISAが始まった2024年は、これまで投資に縁のなかった層が動き出した年でした。私の家でも同じような変化がありました。
少し前、姉から「新NISAってどうなの?」と相談を受け、そのことを記事にまとめたのですが(NISAを家族に相談されたらどう答える?投資を伝える難しさ)、その話をきっかけに親戚の間で「投資に詳しい人」という印象が定着しました。すると、自然と投資の話題が増え、大学生の親戚も新NISAを使って積立投資をしていることを耳にしました。
その大学生は21歳。ちょうど大学3年生で、アルバイト代からコツコツと資金を作り、2024年4月に新NISAの「つみたて投資枠」で投資をスタートしたそうです。投資額は毎月3万円。銘柄は「全世界株式(オルカン)」のように、世界中に分散投資できる投資信託を選んでいました。大きなリスクを取らずに、長期で育てる姿勢が印象的でした。
新NISAとは?初心者にもわかりやすく解説
新NISAは2024年から始まった新しい非課税制度です。これまでのつみたてNISAや一般NISAが一本化され、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを自由に組み合わせて使える仕組みになりました。
つみたて投資枠では、長期・分散・積立の考え方を重視しており、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。年間の非課税枠が拡大されたことで、大学生でも少額から安心して投資を体験できるようになりました。
以下リンクで新NISAの制度解説をしています。
新NISA完全ガイド2025
私の親戚のように、制度のわかりやすさと始めやすさがきっかけで新NISAに関心を持つ若い人は確実に増えています。投資というよりも「お金の勉強を実践している」という感覚に近いのかもしれません。身近な体験を通して、投資が特別なものではなくなってきているのを実感します。
親戚の大学生が新NISAを始めたきっかけ
彼が新NISAに関心を持ったのは、単なる流行ではなく「お金の価値」を考えるようになったからでした。もともとアルバイトで得た収入をきちんと貯金するタイプで、使い道にも慎重でした。しかし、大学の授業で経済や社会の仕組みに触れるうちに、物価が上がっていく現実を知り、「貯金だけではお金の価値が目減りするかもしれない」と感じたそうです。
それが、投資に興味を持つ最初のきっかけになりました。
当初は、投資と聞くと「難しそう」「失敗が怖い」といった印象を持っていたといいます。ところが、最近ではSNSやYouTubeで、初心者向けにわかりやすく解説する動画が増えています。彼もそうした情報に触れるうちに、「自分にもできるかもしれない」と感じたようです。特に“新NISAなら少額から始められる”という点が、行動の後押しになりました。
私自身も新NISAの始め方にフォーカスを当てた記事を書いています。よかったら参考にしてみてください。
積立NISAの始め方|初心者でも簡単にできるやり方【2025年最新版】
僕もよくYouTubeで投資関連の動画見てます!
なんでも解説してくれる人が増えて学びやすい世の中になったね。
投資を始めた当時の状況
彼が投資を始めたのは、2024年4月の新制度開始と同時期。
新生活が落ち着いたころに証券口座を開設し、つみたて投資枠で毎月3万円の積立を始めました。銘柄は全世界株式、いわゆる「オルカン」タイプを選択。世界中に分散投資できる安心感が決め手になったようです。
最初の数か月は値動きに戸惑うこともあったものの、「積立なら気にしすぎないで続けられる」と話していました。YouTubeで得た知識を実践しながら、自分なりのリズムをつかんでいったようです。
新NISAを通じて、彼は“投資を学びながら経験する”という感覚を持つようになりました。最初は小さな一歩でしたが、大学生が自分の意思でお金と向き合う姿勢に、時代の変化を感じます。
次は、実際にどのような銘柄を選んだのかを見ていきます。
積立銘柄はオルカン(全世界株式)
彼が選んだ積立銘柄は「eMAXIS Slim 全世界株式(通称オルカン)」でした。新NISAのつみたて投資枠で運用できる投資信託の中でも、特に人気の高い銘柄です。世界中の株式に幅広く投資できるため、ひとつの国や企業に偏らず、自然と分散投資ができる点が魅力でした。大学生であっても、こうした分散の考え方を意識して選んでいることに驚かされます。
オルカンは、日本や米国、ヨーロッパ、新興国といった多くの地域の企業を組み入れています。つまり、どこか一つの地域の景気が悪くても、他の地域が補うような構造になっており、リスクが分散されやすいのです。長期投資との相性が良く、「コツコツ積み立てていく」という新NISAの考え方にも合致しています。
なぜオルカンを選んだのか
彼は当初、どの投資信託を選べばいいか迷っていたそうです。SNSやYouTubeで情報を集めるうちに、オルカンの評判を多く目にしました。「初心者でもわかりやすい」「手数料が低い」「放置でも安心しやすい」などの意見が多く、自分の性格に合っていると感じたようです。特に信託報酬が低い点は、長期的に見て大きなメリットになります。
実際に投資を始めてみると、値動きがあるたびに不安になることもあったといいます。それでも、世界全体に分散している安心感から、「慌てず続けよう」と思えたとのことでした。初めての投資で選ぶ銘柄としては、仕組みがシンプルで理解しやすい点が決め手になったようです。
オルカンを通じて、彼は「投資=ギャンブルではない」という感覚を実感していました。堅実に資産を育てるという姿勢が、学生のうちから身につくのは大きな意味があります。
次は、実際に1年半積み立てを続けて感じた変化について触れます。
18か月続けた結果と感じた変化
18か月続けた結果と感じた変化
彼が新NISAで積立を始めたのは2024年4月。そこから2025年9月までの18か月間、投資を一度も止めることなく継続してきました。
毎月3万円ずつ、つみたて投資枠でコツコツと積み立てた結果、評価額は少しずつ増えていったといいます。最初の頃は値動きに敏感でしたが、半年ほど経つと「投資は焦らず続けるもの」という感覚に変わっていきました。
18か月間の積立イメージ(例)
| 月 | 基準価額(円) | 累計投資額(円) | 2025年9月評価額(円) | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 24,005 | 30,000 | 30,400 | +1.3% |
| 2024年9月 | 25,150 | 180,000 | 186,300 | +3.5% |
| 2025年3月 | 27,600 | 360,000 | 381,000 | +5.8% |
| 2025年9月 | 30,410 | 540,000 | 611,600 | +7.8% |
(※数値は実際の相場を参考にしたイメージであり、将来を保証するものではありません)
結果として、大きな利益というよりも「着実に増えている」という実感があったようです。投資額が増えるたびに「お金を育てている感覚」が強まり、銀行預金とは違う達成感があったと話していました。彼の印象的な言葉は、「投資って思ったより地味。でも、その“地味さ”が安心につながる」でした。
また同時に、銀行口座に入れているお金がもったいないとも感じたそうです。
大学生からこれだけ資産運用できたら将来有望ですね。
今の日本の経済状況を考えると、逆に学べる環境とも言えるのかも?
途中でやめたくなった時の工夫
もちろん、順調な時期ばかりではありません。
彼も、相場が下がったときには「このまま積み立てを続けていいのか?」と迷う瞬間が何度もあったそうです。特に、海外情勢の影響で株価が大きく下がった時期――いわゆるトランプショックのような急落局面では、不安を感じたと話していました。
それでも彼は、投資をやめませんでした。理由は明確で、「もともと使う予定のない余剰資金で積み立てているから」だといいます。アルバイトで得たお金を貯金口座に眠らせておくより、将来のために“お金の勉強”として動かしている――そんな意識が支えになっていました。
下落時には、むしろニュースや経済情報を通して「なぜ下がったのか」を学ぶようにし、残高はあえて見ないようにしたそうです。値動きに一喜一憂するより、投資を続けることそのものを目的にした結果、自然と不安が減っていったといいます。
彼にとって、投資とはお金を増やす手段ではなく、自分の考え方を鍛える体験でもありました。
続けるうちに、「将来に備えるとはこういうことなのかもしれない」と感じたそうです。
次は、大学生が新NISAを無理なく続けるための工夫について見ていきます。
大学生が新NISAを続けるためのコツ
新NISAを始めたものの、「続けること」が難しいと感じる人は少なくありません。特に大学生の場合、収入が不安定で、学費や生活費とのバランスを取る必要があります。だからこそ、最初から「無理のない金額設定」と「自動積立」の仕組みを整えておくことが重要です。
彼も当初は、毎月3万円の積立を「少し多いかも」と感じていたそうです。しかし、生活費を優先しつつ、アルバイトの中から一定額を投資に回すルールを作ったことで、ストレスなく継続できました。投資は「余ったお金でやるもの」ではなく、「使う前に取り分けるもの」と考えることで、長く続けやすくなります。
また、積立を自動化しておくと、感情に左右されず安定して運用を続けられます。相場の上げ下げを気にせず淡々と積み立てる姿勢が、長期投資では何よりも大切です。
1万円からでも始められるNISAのシミュレーションを以下記事で解説しています。
1万円から始めるNISA
将来を見据えた使い方
大学卒業後も続けられるように、投資の仕組みを早めに整えておくのもポイントです。就職して収入が安定したら、少しずつ積立額を増やすことで、時間を味方にできます。社会人になると支出の内容も変わるため、定期的に運用状況を見直し、「今の自分に合った投資額」に調整していくことが重要です。
また、投資を「お金の勉強」として捉えておくと、相場が下がった時も前向きに捉えられます。結果よりも「続ける習慣」が身につくことが、将来の大きな資産につながるのです。
大学生のうちから新NISAを経験しておくことで、社会に出てからの資産形成に大きな差が生まれます。
次は、まとめとして「時間を味方にする投資の考え方」について見ていきます。
まとめ:早く始めた人ほど気づく「時間の味方」
大学生のうちから新NISAを始める最大の利点は、「時間を味方にできる」という点にあります。投資の成果は、短期的な値動きよりも“どれだけ長く運用を続けられるか”で大きく変わります。時間が長いほど、相場の上下を吸収し、平均化しながら安定的に成長するチャンスが増えるのです。
新NISAでは、生涯で最大1,800万円まで非課税で投資できる仕組みが用意されています。この「非課税枠」を早い段階で活用することで、利益が大きくなっても税金がかからないという恩恵を長く享受できます。たとえば、大学生のうちから積み立てを始めておけば、就職後や結婚後など、ライフステージが変わっても枠を使い続けることができます。
逆に、年齢を重ねてから始める場合、非課税期間のメリットを十分に活かしきれないこともあります。若いうちに始めておくほど「運用期間」と「利益を育てる時間」を多く確保できるのです。
| 元本 | 評価額 | 含み益 | 本来の課税額(約20.315%) | 新NISAの非課税メリット |
|---|---|---|---|---|
| 1,800万円 | 3,600万円 | +1,800万円 | 約 366万円 | 税金がかからず 366万円の差 |
| 1,800万円 | 2,000万円 | +200万円 | 約 40万円 | 税金がかからず 40万円の差 |
また、長期で運用することで、相場が一時的に下がっても慌てずに対応できるという強みもあります。歴史的に見ても、世界全体の株式市場は長い目で見ると右肩上がりに成長してきました。短期的な下落があっても、数年単位で見れば回復しているケースがほとんどです。
つまり、若いうちに始めることは「リスクを取る勇気」ではなく、「時間でリスクをならす工夫」と言えます。
彼のように大学生のうちから少額でも新NISAを始めておくと、将来の資産形成に大きな差が生まれます。焦らず、コツコツと継続することが、将来の安心感につながる第一歩です。
早く始めた人ほど、あとから「やっておいてよかった」と実感する日がきっと訪れます。
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。
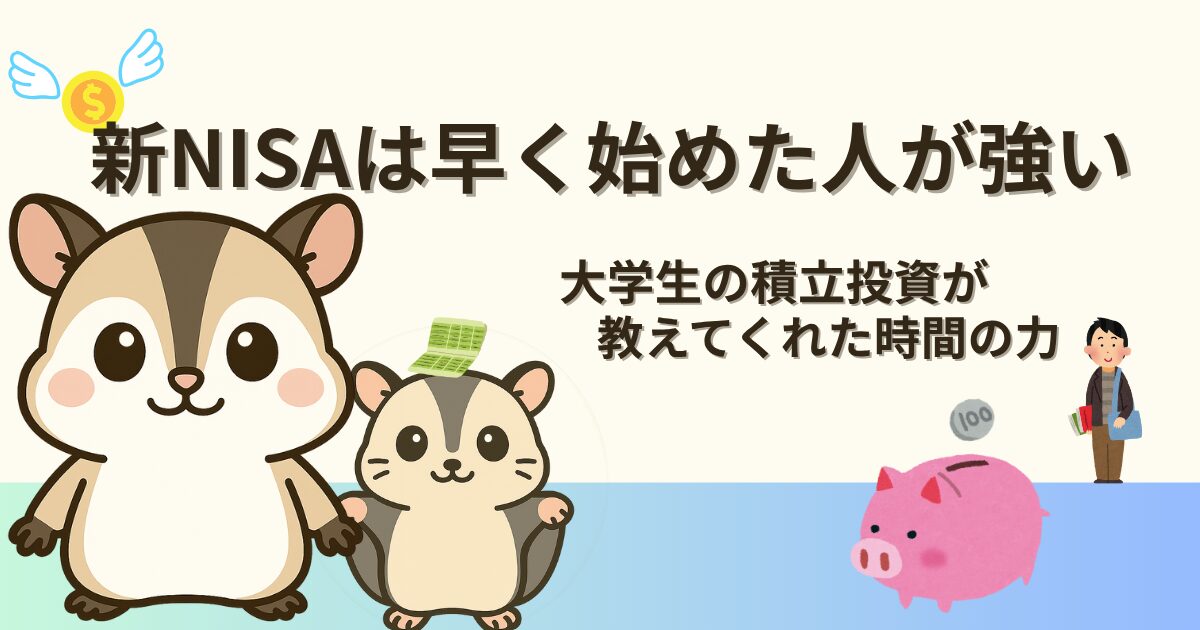


コメント