「積立NISAを始めたいけれど、何から手を付ければいいの?」——そんな迷いを5ステップで解消します。この記事は制度の百科事典ではなく、今日、設定まで完了させるための実践マニュアルです。
私自身、SBI証券で口座を開設し「eMAXIS Slim 全世界株式」に月2万円を積み立てる設定を行いました。最初は評価額がマイナスで不安もありましたが、半年後にはプラスへ転じ、“続けることの大切さ”を実感できました。この記事では、そんなリアルな体験も交えつつ、初心者が迷わず始められる手順を解説します。
なお、制度全体の詳しい比較や「積立投資枠と成長投資枠の使い分け」は別記事【新NISA完全ガイド】で紹介しています。本記事では、積立NISAを今すぐ始めるための流れに絞ります。
積立NISAとは?初心者でも安心の制度ポイント
積立NISAは、少額から長期・分散・積立を支援する非課税制度です。2024年の制度改正(新NISA)でさらに使いやすくなり、2025年現在は以下の仕組みになっています。
- つみたて投資枠:年間120万円
- 成長投資枠:年間240万円
- 合計:年間360万円/生涯投資枠1,800万円(うち成長枠1,200万円)
- 非課税期間は無期限/売却すると翌年以降に、生涯投資枠が復活して再利用可能
対象商品は金融庁が基準を定めた投資信託に限定されており、初心者でも極端なリスクを避けやすいのが特徴です。私は実際に積立を始めてから「買付や積立設定が自動化される安心感」を体感しました。投資を特別な行為にするのではなく、日常生活に組み込めるのが積立NISAの魅力です。
コツコツ型に最適。相場に一喜一憂せず、生活リズムに“積み立て”を組み込もう。
毎月の自動引き落としにしておけば、手間ゼロですね!
積立NISAの始め方を5ステップで解説
ステップ1:金融機関を選ぶ
最短で迷わず進むコツは、はじめに“続けやすさ”で選ぶこと。
私はSBI証券を使っています。
理由は、①アプリ操作が直感的で積立変更が数タップ、②つみたて対象ファンドが豊富、③クレカ積立など還元施策がある、の3点でした。もちろん楽天証券なども有力。
大切なのは「アプリが自分に合うか」「必要な商品があるか」「積立が自動化しやすいか」という日常運用の目線です。
「銀行窓口でも開設はできますが、商品数・手数料・アプリの使い勝手を総合するとネット証券が有利です。迷ったら、まずは比較の考え方を押さえておきましょう → NISAは銀行?ネット証券?初心者が迷わない口座開設の選び方【2025年最新版】」
手順はシンプルで、
(1)証券総合口座の申込み→(2)本人確認→(3)NISA口座の設定の順。途中で「課税口座」だけで進めてしまう人がいるので、NISA(つみたて投資枠)を選び忘れないのがポイントです。
氏名・住所・マイナンバー確認が済むと、数日〜1週間ほどで取引開始の通知が届きます。
私は土日に申請し、翌週半ばに口座が有効化されました。
まずは「毎月続けられる環境」を整えるのが勝ち筋だよ。
アプリが使いにくいと、そこで挫折しそうですもんね。
最初に時間を使うのは口座選びだけ。ここを越えたら、残りは“積立の自動化”で勝手に回ります。
ステップ2:「つみたてNISAのやり方」を理解する
積立NISAは決めた日・決めた金額を自動で買う仕組み。だからこそ、続けやすい初期設定が要です。
金額は月1,000円からでもOK。私は最初月2万円に設定し、固定費の見直し後に月3万円へ増額しました。
コツは、給料日直後を積立日にしておくこと。先に投資を“取り分け”てしまえば、生活費と混ざらず無理なく継続できます。
頻度は「毎月」が基本。日次・週次積立も選べますが、初心者は管理が簡単な毎月で十分です。ボーナス月に増額できる金融機関もあります。
なお、積立設定はあとから一時停止・増額・再開が柔軟に可能。たとえば相場下落で不安になった月は止めるのではなく、少額に下げて「継続だけは死守」するのが上達の近道でした(私の経験)。買付が遅れて機会を逃すより、細く長く続けるほうが結果に効きます。
設定画面では、①ファンド名、②積立金額、③買付日、④引落方法(銀行/クレカ)、⑤口座区分(NISA)を確認して確定。ここでNISAが選べているかだけは毎回チェックを。私は一度、特定口座で買い付けてしまい、慌てて設定し直したことがあります。こうした初歩ミスは確認リストを用意すると防げます。
最後に、積立は「始めたら放置」ではなく“見すぎない見守り”が大切。私は月1回、アプリで評価額と積立履歴を確認し、年1回だけ家計と照らして金額を見直します。上下の値動きに振り回されず、仕組みで勝つ意識に切り替わります。
【初期設定メモ】 積立日は毎月27日、引落はSBI証券なので三井住友カードに設定。最初は2万円、固定費カット後5万円に2025年3月から増額しました。
ステップ3:投資信託を選ぶ
積立NISAの商品選びで迷ったら、次の3つだけをチェックすれば大きく外しません。
- 手数料が安い(信託報酬は年0.2%以下)
- 純資産残高が十分(目安100億円以上、できれば300億円超)
- 広く分散されている(全世界株式や米国株式〈S&P500〉など)
「基準の背景やチェック方法をもう少し深掘りしたい方は、こちらで解説しています → 投資信託の選び方|初心者が失敗しない3つのポイント【2025年版】」
私は最初に純資産が少ない商品を検討しましたが、繰上償還の不安があり断念。結果的に「eMAXIS Slim 全世界株式」を選びました。低コスト・規模・分散というシンプルな基準に沿えば、初心者でも安心して長期で持ち続けられます。
S&P500と全世界で迷い、為替偏りを避けたいこと、新興国も少量取り込みたい理由で全世界を選択。日経平均高配当利回り株ファンドも途中で追加しましたが信託報酬が高い事に気付き売却検討中。
ステップ4:積立額と期間を決める
投資は「継続」が最優先。だからこそ、最初は無理のない金額から始めるのが鉄則です。目安は月1万〜3万円。私は月2万円でスタートし、格安スマホへの乗り換えで浮いた分を積立に上乗せしました。
おすすめは、家計管理を 固定費 → 投資 → 貯蓄 → 変動費 の順で配分すること。投資を生活の“残り”ではなく“先取り”にすることで、自然に続けやすくなります。
積立額は途中で変更可能なので、相場が下がってもゼロにせず「少額でも続ける」ことが重要。長期では積立年数の方が効くため、額より継続を優先しましょう。
「固定費を見直して投資を“先取り”するコツは、こちらで実例つきで紹介 → 無理せず続けられる節約術|小さな工夫で月5,000円浮かせる方法」
ステップ5:積立設定をして開始
最後は積立設定です。流れは次のとおり:
- 対象ファンドを検索して登録
- 積立額・日付・引落方法を入力
- NISA口座(つみたて投資枠)を選択して確定
私の場合は、毎月2万円・給料日直後・クレカ積立で設定。これで翌月から自動的に買付が始まりました。最初の設定作業は5分程度で終了。その後はアプリで月1回チェックする程度でOKです。
また、先にも説明していますが、必ずNISA口座を選択してください。ここだけは、必ずチェックするように、注意しましょう。
最初の一手間で、あとは“自動投資マシン”が動き続けるよ。
忙しくても放置で増えるなら、確かに続けやすいですね!
FAQ|積立NISAでつまずきやすいポイントと解決策
Q1. 評価額がマイナスになったらどうする?
私も開始から3か月ほどはマイナス表示に焦りました。でもこれは積立投資の“安く仕込めるチャンス”。下がったときほど買付口数が増えるため、後々の回復局面でプラスに転じやすいのです。実際、半年ほど継続したら含み益に変わりました。
→ 心理的に不安なときの考え方は 積立NISAや投資信託は元本割れする?怖さを解消する考え方と体験 で詳しく解説しています。
2024年8月に評価額が –8.4% まで下落し、不安で解約寸前まで考えました。そこから「①売らない、②積立は止めない、③アプリは月1回だけ確認」という3ルールを自分に課したことで、翌年には含み益に回復。続ける強さを実感しました。
Q2. 商品を途中で変えてもいい?
可能ですが、売却時に税制上の扱いが発生したり、手数料・信託財産留保額がかかる場合もあります。私は最初に日本株型を検討しましたが、途中で全世界株式に一本化しました。結果的にシンプルで管理がラクに。初心者はまず低コストのインデックスファンド1〜2本に絞るのが安心です。
Q3. いくらから始めるのが正解?
「家計が崩れない範囲」が正解です。私も最初は月1万円から。慣れて仕組みに安心感が出てきた段階で2万円、3万円へと増額しました。金額よりも継続年数の方がリターンに効くため、まずは少額からでも始めることが大切です。
Q4. 非課税枠は必ず使い切るべき?
理想は使い切りですが、教育費・住宅費などライフイベントとのバランスも重要です。余力が生まれたら段階的に増額で十分。私は「格安スマホに切り替えた差額」を積立に回し、無理なく非課税枠の利用を広げています。
→ 節約で投資余力をつくるコツは 無理せず続けられる節約術|小さな工夫で月5,000円浮かせる方法 にまとめています。
積立NISAの運用メンテナンス方法
積立NISAは“ほったらかし”が基本。ただし、完全放置ではなく年1回の点検を習慣にすると安心です。
- 年1回の点検:家計の状況を見直し、積立額を調整。昇給やボーナス時に増額するのがおすすめ。
- 商品チェック:インデックスファンドは基本的に変更不要。ただし純資産残高や運用方針に大きな変化がないか確認。
- 日常の確認:アプリで月1回、積立が予定通り実行されているかを見る程度で十分。見すぎると下げ相場で不安になり、売却したくなるので要注意。
私の場合、2024年の夏に一度アプリを見すぎてしまい、含み損に落ち込んで解約しそうになりました。しかし「積立は未来のため」と切り替え、“見すぎないルール”を設けたことで今は淡々と継続できています。
積立NISAは“仕組み化して続ける”のが一番。
たしかに、年1回の点検なら忙しくても続けられそうですね!
私は毎年12月に次の5項目を確認しています。①家計余力(年間貯蓄額)②積立額(前年2万円→今年5万円に増額)③信託報酬の改定有無④純資産残高の伸び⑤目標配分との差。これで「やめる理由がない」と確認でき、安心して新年を迎えられます。
まとめ|積立NISAの始め方はシンプルに5ステップ
ここまで、積立NISAを始める流れを 初心者でも迷わず実践できる5ステップ として解説しました。
- 金融機関を選ぶ
ネット証券を中心に、アプリの使いやすさや商品数で選ぶのが安心。詳しくは NISAは銀行?ネット証券?初心者が迷わない口座開設の選び方【2025年最新版】 を参照してください。 - 積立の仕組みを理解する
毎月自動で買付されるため、一度設定すれば“ほったらかし投資”が可能。給料日直後に設定すると生活費と混ざらず続けやすいです。 - 投資信託を選ぶ
「低コスト・純資産の規模・広い分散」が3原則。私は「eMAXIS Slim 全世界株式」を選びました。選び方の詳細は 投資信託の選び方|初心者が失敗しない3つのポイント【2025年版】 で図解しています。 - 積立額と期間を決める
月1万円からでもOK。私は2万円から始め、節約で生まれた余力を3万円に増額しました。大切なのは“ゼロにせず継続すること”。 - 積立設定をして開始
ファンド選択→積立額→日付→引落方法→NISA口座を確認して完了。5分で設定でき、翌月から自動で買付がスタートします。
継続のコツと心構え
- 相場に一喜一憂しない:評価額が下がったときは“安く仕込めるチャンス”。
- 年1回の点検で十分:積立額の見直しは昇給や節約のタイミングに。
- 少額でも続ける:金額よりも継続年数が資産形成に効いてきます。
実際に私も、最初は不安を抱えながらのスタートでしたが、半年〜1年と続けるうちに「積立NISAは仕組み化すれば難しくない」と確信できました。
関連記事(あわせて読みたい)
投資は小さな一歩から
積立NISAの魅力は、「今日決めた設定が、10年20年先の資産を作る」という点にあります。大きな額でなくても、“時間を味方につける”ことこそ最大の武器。
もし迷っているなら、まずは月1,000円からでもスタートしてみてください。未来の自分が「やってよかった」と思える日がきっと来ます。
投資は始める勇気より、続ける仕組みがカギだよ。
じゃあ今日から“自動積立”を仲間にしてみます!
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。

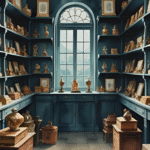

コメント