はじめに
「積立NISA(投資)は怖い」と感じるのは自然なこと
私自身も初めて投資に関心を持ったとき、「投資って怖そうだ」と感じました。
預貯金中心の方にとって、値動きによって元本を下回る可能性があると聞けば不安になるのは当然です。実際、金融庁のNISA特設サイトでも「株式や投資信託は元本割れのリスクがある」と明記されています。(金融庁 NISA特設サイト)
さらに、投資信託協会の調査結果でも、投資をしない理由として「損をしそうで怖い」「元本保証がない」といったリスクへの不安が一定数挙げられていることが公表されています。(投資信託協会 統計・レポート一覧)
とはいえ、不安を持つこと自体は悪いことではありません。重要なのは、その不安を出発点に制度の仕組みや商品の特性を学ぶことです。それが結果的に、自分に合った投資判断につながります。
投資は怖いと感じるのが普通なんだよ
先生も最初はそうだったんですか?
もちろん。不安を持ったからこそ慎重になれたんだ
不安を持つことで慎重な選択ができる
投資の不安は「大きな失敗を避けるためのブレーキ」になります。
たとえば、知識がないまま大きな金額を投じてしまえば、相場の変動に耐えきれず途中でやめてしまう可能性があります。
不安を持っている人は、少額から始める、制度をしっかり確認する、といった冷静な行動につながりやすいのです。私自身も最初は月5,000円から始めましたが、もし一気に数十万円を投じていたら途中でやめていたかもしれません。
「不安=悪いもの」と捉えるのではなく「不安=安全装置」として活かすことが、積立NISAを長く続けるポイントになります。
次は、実際に私が最初に感じた「積立NISAの不安」について詳しく紹介します。
積立NISAで最初に感じた不安
元本割れしないか心配だった
積立NISAを始める前に一番強く感じたのは「元本割れしたらどうしよう」という不安でした。
銀行預金は減ることがないのに、投資信託は値動きによって増えたり減ったりします。たとえば、10万円積み立てたのに相場が下がって9万円になってしまう可能性があると聞くと、正直怖さを覚えました。
私の場合、夫婦で生活費を分担しているため「投資でお金を減らしてしまったらどうしよう」と考えることが多かったです。とくに共働きで子どもがいない今はまだ余裕がありますが、将来のために貯金もしておきたいという思いもあり、投資とどう両立するかが悩みでした。
ただ実際に調べてみると、積立NISAは「長期投資」が前提であり、短期的な元本割れはあっても、時間をかけて成長する企業の利益を取り込む仕組みになっていると理解できました。長期投資のシミュレーションを見ると、相場の下落があっても長期でプラスに転じるケースが多いことがわかり、不安が少し和らぎました。
投資詐欺のイメージが強くて怖かった(体験談)
私が積立NISAを始めるのをためらった大きな理由の一つが「投資=詐欺」というイメージでした。これは、親戚が過去に投資詐欺に巻き込まれた経験があるからです。
10年以上前、親戚が「必ず儲かる」という話を信じて数百万円を投資しました。しかし実際には詐欺で、全額を失ってしまったのです。そのときの落ち込みや生活の変化を間近で見ていたので、「投資」と聞くだけで危ないものという印象を持っていました。
その経験から、私自身も最初は「NISAも何か怪しい制度なのでは?」と疑っていました。ですが調べていくうちに、積立NISAは金融庁が監督する公的な制度であり、投資できる商品も厳しく選ばれた投資信託やETFに限られていると知りました。この点が、詐欺まがいの話とはまったく異なると気づきました。
「投資=怖い」という思い込みは簡単には消えませんが、公式情報をしっかり確認することが不安を乗り越える第一歩だと実感しました。
調べて分かった積立NISAの仕組み
金融庁が示す制度の目的と安心材料
積立NISAを詳しく調べて分かったのは、この制度が「国が国民の資産形成を支援するため」に作られているという点です。金融庁の公式ページによると、積立NISAは少額から長期・積立・分散投資を行うための非課税制度で、長期的に資産を育てることを目的としています(金融庁:NISA特設サイト)。
具体的には、新NISAでは年間120万円までの投資が非課税で運用でき、生涯で最大1,800万円まで投資可能となっています。そのうち積立枠は年間120万円までで、投資信託などをコツコツ積み立てていく仕組みです。
実際に金融庁が示すシミュレーションを見ると、以下のように「長期・積立・分散」を意識することで安定した成長が見込めるケースが多いと分かります。
| 投資期間 | 毎月積立額 | 想定利回り3% | 想定利回り5% |
|---|---|---|---|
| 10年 | 1万円 | 約140万円 | 約155万円 |
| 20年 | 1万円 | 約280万円 | 約410万円 |
| 30年 | 1万円 | 約490万円 | 約830万円 |
このように「国が制度を作り、商品も金融庁が認めたものだけ」という点が、詐欺的な投資話とは大きく異なり、安心材料のひとつになりました。
私もこの点を理解してから、不安よりも「長く続ければ増える可能性がある」という前向きな気持ちに切り替えられました。
投資信託の商品選びに関する基本知識
制度を理解した次のステップは「どの商品を選ぶか」でした。積立NISAで購入できる投資信託は数百種類あり、どれを選んで良いか迷うのが普通です。
私が参考にしたのは、まず証券会社が発表している「積立NISA人気ランキング」でした。楽天証券やSBI証券などでは、実際に多くの人が積み立てている商品をランキング形式で公開しています。これを見ると、インデックス型の投資信託(たとえばS&P500や全世界株式に連動するもの)が上位を占めていることがわかります。
ただし、1社のランキングだけで決めるのは危険だと感じました。
そこで、複数の証券会社が公表している投信ランキングを横断的に確認し、同じ銘柄が複数社で上位にいるかを見比べました。特に「信託報酬(手数料)の低さ」「純資産残高の多さ」「運用実績の長さ」の3点は、初心者でも判断しやすいシンプルな基準だと考えています。結論として、単独のランキングに依存せず、複数の情報源で相対評価することが重要です。
この過程で学んだのは「人にすすめられたから選ぶのではなく、自分で納得できる根拠を持って選ぶことの大切さ」です。積立NISAを始める前に知りたかった情報を整理しておいたので、別記事でまとめています → 投資信託の選び方
ランキングって、ついつい見ちゃいますよね!
信用できる発信元である必要はあるから、複数情報で確かめよう。
実際に始めてみたときの体験
月5000円からスタートしたリアルな変動
私が積立投資を実際に始めたのは、新NISAが始まる前の2019年頃でした。
最初は「損をしても生活に影響がない金額」である月5,000円から積立をスタートしました。毎月の固定費に大きな余裕はありませんが、5,000円なら趣味を少し我慢すれば続けられると判断しました。
最初の1カ月目、投資した5,000円が数日後に数百円下がっていて正直驚きました。反対に翌週には数十円プラスに戻っていて、「上がったり下がったりするんだ」と実感しました。預金とは違い、金額が日々変わることを目の当たりにしたのは初めてで、怖さと同時に「どうなるんだろう」と興味が湧きました。
1年間続けてみると、トータルで投資額60,000円に対して評価額は約63,500円になりました。増えたのはたった3,500円ですが、毎月積み立てたお金が「働いてくれている」と感じられたのは大きな経験でした。これがなければ、積立NISAを続けていなかったと思います。
少額から始めることで不安を小さくできた
実際に月5,000円から始めてみて感じたのは、「少額だからこそ不安を小さくできた」ということです。もし最初から数万円を投じていたら、値動きのたびに気になって続けられなかったかもしれません。
少額から始めると、仮に値下がりしてもダメージが小さく、「勉強代」として受け入れやすいです。私も最初の1年間は「お金が増えた・減った」という結果よりも、「投資信託がどう動くのか」を体験できたことが一番の収穫でした。
さらに、夫婦で話し合いながら少しずつ増額していくスタイルにしたことで、家計に無理なく投資を続けられています。これは共働き家庭にとって大きな安心材料でした。
初心者にとって「まずは小さく試してみる」という行動は、不安を和らげる最良の方法だと思います。積立NISAの魅力は「月100円からでも始められる」点なので、怖いと感じる人こそ小さくスタートしてみる価値があります。
積立NISAのリスクと向き合う方法
損をする可能性と長期投資でのカバー
積立NISAを始めるときに理解しておきたいのは、「元本割れの可能性はゼロではない」という点です。どんなに優れた投資信託でも、短期的には相場の影響を受けてマイナスになることがあります。
ただし、金融庁のシミュレーションでも示されているように、長期で積み立てるほど損をする確率は下がっていきます。これは、投資先が一時的に下がっても、時間をかけて回復しやすいためです。特にインデックス型の投資信託は世界中の企業に分散投資しているため、全体の経済成長を取り込める仕組みになっています。
私自身、最初の数カ月はマイナスになることもありましたが、1年、2年と続けてみると「下がるときもあるけれど、時間をかければ回復する」という流れが体感できました。大切なのは「短期の数字に一喜一憂しないこと」だと実感しています。
初心者の方は「積立NISAは必ず儲かる」と誤解せず、「長期で運用することでリスクを和らげる」と理解しておくと安心です。
詐欺被害を避けるための確認ポイント
積立NISAは金融庁が定めた公的制度ですが、周囲には「これに投資すれば必ず儲かる」という怪しい話も存在します。実際、私の親戚が数百万円の投資詐欺に遭った経験を思い出すと、いかに事前の確認が大切か痛感します。
詐欺を避けるために意識しているチェックポイントは以下の3つです。
- 公式情報を必ず確認する:金融庁や証券会社の公式サイトに載っていない商品や仕組みは避ける
- 「必ず儲かる」という言葉を信じない:投資に100%は存在しない
- 契約前に家族と共有する:冷静な目線で第三者に確認してもらう
これらを実践することで、怪しい話に巻き込まれるリスクを減らせます。
ただ、こうした確認を徹底していても、詐欺の誘いは意外なところからやってきます。
特に投資の世界では、「金融庁の制度に似せた架空の商品」や「NISAをきっかけに別の高利回り投資を勧誘する話」が横行しています。
最初は合法的に見えても、最終的には高額な手数料や実体のない商品につながるケースもあります。
だからこそ、制度として安心できる積立NISAを使う際も、「公的制度の範囲内かどうか」を常に意識することが重要です。
投資は「増やすこと」だけでなく「守ること」も大切です。積立NISAを安心して続けるためには、制度そのものへの信頼に加えて、身近な勧誘や甘い言葉に流されない姿勢がが不可欠です。
よくある質問(FAQ)
積立NISAは本当に安全なの?
積立NISAは「金融庁が定めた公的な制度」であり、対象となる商品も厳しい基準を満たした投資信託やETFに限定されています。そのため、制度そのものは信頼できると考えてよいでしょう。ただし「元本保証」ではない点には注意が必要です。
安全性を理解するうえで大切なのは、「積立NISAは仕組みが透明である」ということです。対象商品は証券会社の購入ページや目論見書で公開されていますし、証券会社を通じて誰でも同じ条件で購入できます。これは、特定の人だけが得をするような怪しい投資話とは大きく違う部分です。
私自身も、最初は「安全なの?」と疑っていましたが、公式情報を確認することで不安が小さくなりました。さらに、実際に数年続けて「元本割れしてもその後に回復する」という流れを体験したことで、制度の信頼性を実感しています。
途中でやめたらどうなる?
積立NISAは途中でやめてもペナルティはありません。積み立てた投資信託を売却すれば、その時点の評価額でお金を受け取ることができます。利益が出ていれば非課税で受け取れますし、損が出ていればそのまま引き出す形になります。
ただし、一度使った「非課税枠」は戻ってこない点には注意が必要です。たとえば、年間40万円分を積み立てて売却した場合でも、その分の枠が再利用できるわけではありません。非課税のメリットを活かすなら、できるだけ長く続けることが有効です。
私の場合、最初の2年目に一度「やめようかな」と思ったことがありました。評価額が少し下がっていたため不安になったのです。でも、売却してしまえば非課税のメリットを失うことが分かり、最終的に続ける選択をしました。その後、数カ月で評価額がプラスに転じたので「やめなくてよかった」と強く感じました。
関連する記事として、積立NISAとiDeCoの違いを比較した内容をまとめています → iDeCoと積立NISAの違い
まとめ
焦らず少額から始めてみる
これから始める方は、制度の仕組みを理解した上で具体的なステップを踏むと安心です。初心者向けに口座開設から最初の積立までを整理した記事もあります → 積立NISAの始め方|初心者でも簡単にできるやり方【2025年最新版】
積立NISAを始める前は「怖い」「損をしたらどうしよう」という不安が大きいものです。私自身も月5,000円からスタートし、最初は元本割れにドキッとしました。しかし、少額だからこそ冷静に観察でき、続けるうちに「投資は上下を繰り返しながら成長していくものだ」と実感できました。
初心者にとって大切なのは「焦らず少額から始めること」です。月100円からでも始められるのが積立NISAの魅力なので、まずは制度を体験し、自分のお金がどう動くのかを確認するところから始めるのが安心です。小さく始めて経験を積むことで、不安は自然と小さくなっていきます。
必ず公式情報を確認し、自分で納得して決める
積立NISAに関しては、友人やネット上の情報だけを頼りにせず、必ず金融庁や証券会社の公式サイトを確認することが重要です。詐欺被害の多くは「知識不足」や「他人任せ」が原因になっています。
実際に私の親戚も投資詐欺で数百万円を失いました。その経験を見てきたからこそ、私は「自分で調べ、自分で納得してから決める」という姿勢を大切にしています。
また、投資の世界では「必ず儲かる話」は存在しません。
本当に儲かるなら、人にすすめず自分だけで続けるはずだからです。誰かの言葉をそのまま信じるのではなく、必ず公式情報に立ち返りましょう。
記事内で紹介したように → 投資信託の選び方 や iDeCoと積立NISAの違い も参考にして、自分に合った方法を考えるのが大切です。
最後に、私自身も積立NISAを通じて「投資は怖いものではなく、知識と仕組みを理解すれば味方になる」と学び直しました。この視点を持てたことで、今では投資を家計の一部として自然に取り入れられています。
投資に関する免責事項
本記事の内容についての注意点
本記事で紹介した内容は、筆者が積立NISAを実際に体験し、調べた情報をもとにまとめたものです。ただし、ここで説明している仕組みやシミュレーションは、あくまで一般的な情報に過ぎません。将来の運用成果を保証するものではなく、記事内容が常に最新であることもお約束できません。
金融庁や各証券会社の制度説明ページは随時更新されるため、実際に積立NISAを始める際には、必ず公式サイトを確認してください。具体的な投資判断にあたっては、公的情報や利用予定の証券会社の説明資料を必ず参照するようにお願いします。
投資判断は必ずご自身の責任で
当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません
積立NISAを含む投資は「元本割れのリスク」を伴います。たとえ長期運用でも、必ず利益が出るわけではありません。投資額・運用期間・商品選びによって結果は大きく異なります。
そのため、実際に投資を行うかどうか、またどの商品を選ぶかは、必ずご自身の判断と責任で決定してください。他人からのすすめや、インターネット上の断片的な情報だけで判断するのは避けましょう。
筆者自身も、夫婦で話し合いながら月5,000円から積み立てを始めました。小さくスタートし、リスクを理解しながら続けることで安心して投資を続けられています。このように「自分で納得すること」が最も大切なポイントです。


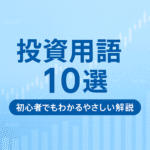
コメント