月5,000円の積立でも、長期になるほど銀行預金とNISA投信の差は大きく開きます。本記事では、年0.1%(預金)と3%/5%/7%(投信)の前提で、5年・10年・20年の将来価値を月次複利で試算しました。注意点や始め方もまとめ、初心者でも迷わない実践手順まで整理します。
カギは「時間×複利」。金額が小さくても、積み上げと時間が効くんだ。
たった月5,000円でほんとに差が出るの?数字を早く見たい!
本記事の結論(先に要点)
- 同じ月5,000円でも、NISA投信(年5%想定)は20年で約2,029,022円、預金(年0.1%)は1,212,024円。差は約816,999円(概算)。
- 差は年数に比例して拡大。5年<10年<20年の順で差が広がる。
- 投信には価格変動リスクがあるため、短期で結果を求めず長期・分散・低コストで粘るのが基本。
比較の前提(試算条件)
- 毎月の積立額:5,000円(年6万円)
- 積立期間:5年(60回) / 10年(120回) / 20年(240回)
- 銀行預金の金利:年0.1%(便宜上)
- 投資信託の想定リターン:年3% / 5% / 7%(手数料控除後イメージ。将来を保証するものではありません)
- 複利計算:月次複利(毎月末に5,000円を積立。将来価値=5,000円×{[(1+i)n−1]/i}、i=(1+年率)1/12−1)
- 元本:5年30万円/10年60万円/20年120万円
- 税金:NISAは運用益非課税。預金利息は課税(20.315%)だが、本比較の金利水準では差への影響は小さい。
制度や用語の不安は、まずは基礎から固めましょう。詳しくは積立NISAの悩みと不安を徹底解消【2025年最新制度対応】が役立ちます。
5年・10年・20年の将来価値(月5,000円)
5年(60か月)|元本30万円
| 運用前提 | 将来価値(概算) |
|---|---|
| 銀行預金(年0.1%) | 300,738円 |
| NISA投信(年3%) | 322,905円 |
| NISA投信(年5%) | 339,069円 |
| NISA投信(年7%) | 355,979円 |
5年は投資期間としてはまだ短く、差は限定的です。とはいえ「同額を積み立てているのに結果が変わる」という感覚を持つには十分な差が見えます。
10年(120か月)|元本60万円
| 運用前提 | 将来価値(概算) |
|---|---|
| 銀行預金(年0.1%) | 602,983円 |
| NISA投信(年3%) | 697,240円 |
| NISA投信(年5%) | 771,816円 |
| NISA投信(年7%) | 855,259円 |
10年になると複利の寄与がはっきりします。年5%想定と預金の差は約168,832円。ここから先、年数が伸びるほど差は一段と拡大します。
20年(240か月)|元本120万円
| 運用前提 | 将来価値(概算) |
|---|---|
| 銀行預金(年0.1%) | 1,212,024円 |
| NISA投信(年3%) | 1,634,272円 |
| NISA投信(年5%) | 2,029,022円 |
| NISA投信(年7%) | 2,537,682円 |
20年は「複利が本気を出す」期間です。年5%想定と預金との差は約816,999円。数字だけでなく、人生イベント(教育、住宅、老後)と積立期間をリンクさせると、納得感が高まります。
リスク直視:下振れケース(参考)
相場は上げ下げを繰り返し、短中期ではマイナスになる時期もあります。極端な机上例として、年−10%が続いた場合の将来価値は次の通りです(毎月末積立、月次複利)。
| 期間 | NISA投信(年−10%) | 元本 |
|---|---|---|
| 5年 | 234,230円 | 300,000円 |
| 10年 | 372,541円 | 600,000円 |
| 20年 | 502,438円 | 1,200,000円 |
現実には「ずっと−10%」の連続は稀で、下落と上昇が交錯します。だからこそ生活防衛資金は預金で確保しつつ、投資は長期視点で淡々と続けるという役割分担が重要です。家計の土台づくりは資産運用を始める前にやるべき家計管理のコツを参照ください。
勝ち筋の設計図(はじめ方3ステップ)
- 目的と期間を固定:教育15年、老後30年など。期間が長いほど積立に有利。
- 商品は低コスト指数連動:全世界株式 or 米国株式のインデックス型。分散が効き、手数料が低い。
- NISAの非課税枠を活用:利益への課税がないため、複利の効き方が段違い。
積立日は「給料日直後」が鉄則。先取りで“使い切り”を防ごう。
アプリが使いやすい会社がいいな。どこから始めれば?
口座さえできれば、ファンド1本を選んで「毎月5,000円の自動積立」をセットするだけです。
NISA投信の選び方(チェックリスト)
- 信託報酬:年0.2%未満を目安に、長期で効くコストを削る。
- 分散性:全世界株式 or 大型分散の指数(MSCI ACWI、FTSE Global、S&P 500 など)。
- 純資産・資金流入:規模があり、継続して資金が流入しているファンドが無難。
- 積立対応:新NISAの積立枠で買えるかを確認。
- 販売会社の使い勝手:アプリUI、クレカ積立のポイント還元、入出金のしやすさ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 月5,000円でもやる意味はありますか?
あります。小さな金額でも長期で複利が効き、差が大きくなります。この記事の20年比較では、年5%想定で約816,999円の差(預金比)が生じました。
Q2. どのファンドを選べばいいですか?
原則は低コスト×分散×指数連動です。全世界株式か米国株式のインデックスが「迷ったら」の定番。信託報酬・純資産・積立対応の三点でチェックしましょう。
Q3. 暴落が怖いのですが、どう向き合えばいい?
生活防衛資金(目安:生活費3〜6か月)は預金で確保し、投資は長期の自動積立を継続。目的時期が近づいたら段階的に現金化するのが基本です。
まとめ:金額より「時間」。今日がいちばん若い日
同じ月5,000円でも、時間が複利を後押しして結果が変わります。短期で焦らず、家計の土台を整え、低コストの指数連動ファンドで長期・分散・自動化を徹底しましょう。続けるほど「差」は大きくなります。
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。
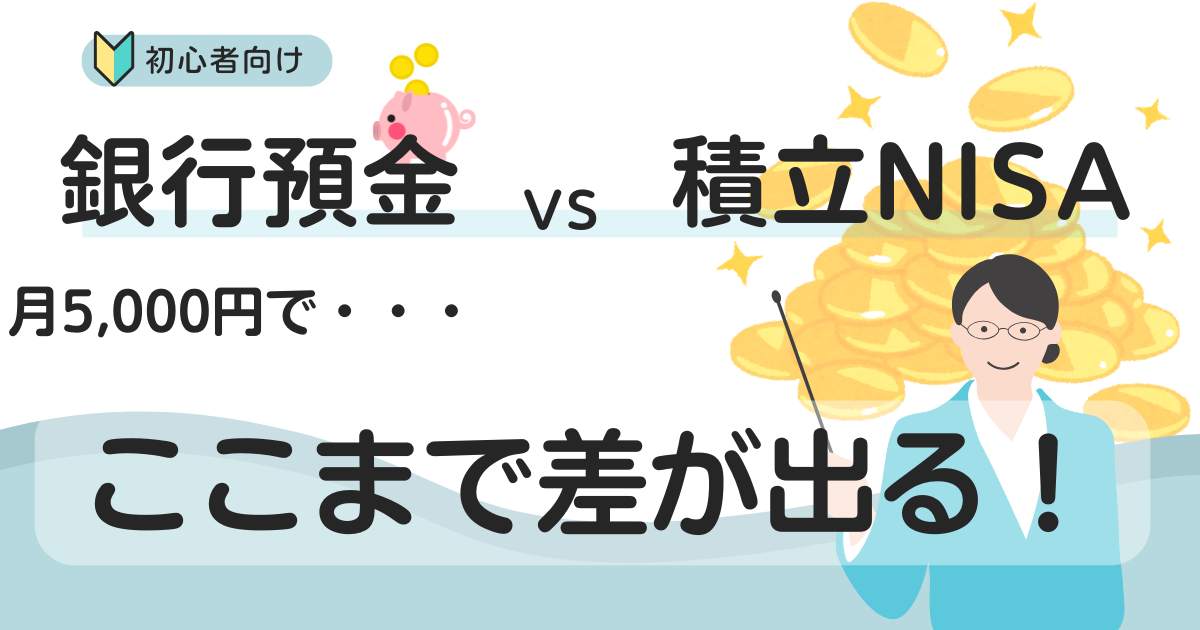


コメント