NISAを始めようと考えたとき、銀行で口座を作るべきか、それともネット証券にするべきか迷う人は少なくありません。
実際どちらを選ぶかで投資の選択肢・手数料・セキュリティの安心感に大きな違いが出ます。
本記事では銀行とネット証券を徹底比較し、初心者が失敗しないための選び方を解説します。
NISAを始めるときの疑問「銀行?ネット証券?」
NISAの認知度が高まり、資産形成を始める人が急増しています。
最初のハードルとなるのが「どこで口座を開設すべきか」という問題です。
金融庁の統計によれば、銀行でNISAを開設する人はいまだ一定数いますが、ここ数年は手数料や利便性の観点からネット証券を選ぶ人が大きく増えています。
ただし、銀行とネット証券では取り扱える商品・手数料・サポート体制・セキュリティなどに明確な違いがあります。
どちらを選ぶかによって、その後の投資体験や成果に直結するため、事前に理解しておくことが大切です。
資産運用とは?初心者が失敗しないための基本と成功へのステップ
ここからは、銀行とネット証券それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、初心者が後悔しないための選び方を解説していきます。。
銀行でNISAを開設するメリット・デメリット
メリット
- 窓口相談できる安心感
初めて投資をする人にとって、「人に直接相談できる」というのは大きな安心材料です。
銀行では専門スタッフが対応してくれるため、心理的なハードルは低くなります。 - 預金とまとめて管理できる
給与振込や貯金と同じ銀行でNISAを開設すれば、一元管理が可能です。
デメリット
- 商品数が限られる
銀行で取り扱う商品は投資信託中心で、数も限られます。
株式やETFに直接投資することはできません。
投資信託の選び方|初心者が失敗しない3つのポイント【2025年版】 - 手数料が高め
販売手数料が年1〜2%台に設定されていることも珍しくなく、長期投資では大きなコスト差になります。 - 担当者の提案が必ずしも最適とは限らない
ノルマを意識した提案になる可能性もあり、投資家本人にとってベストとは限りません。
ネット証券でNISAを開設するメリット・デメリット
メリット
- 取り扱い商品の幅広さ
投資信託はもちろん、株式・ETFなど幅広い金融商品に投資できます。 - 購入手数料無料が一般的
ネット証券の多くは投資信託の購入手数料がゼロ。信託報酬も低水準の商品が充実しています。 - 利便性が高い
スマホやパソコンから24時間取引できるため、忙しい社会人でも活用しやすいのが特徴です。
デメリット
- 対面相談ができない
サポートは電話やチャットが中心。人に会って相談したい人には不安に感じることもあります。 - 情報収集を自分で行う必要
多くの選択肢の中から、自分で勉強しながら選ぶ姿勢が求められます。
実際のコスト比較
新NISAのつみたて投資枠については、すべての金融機関で購入手数料が無料と定められています。これは金融庁が定めたルールであり、制度上の安心材料です(金融庁)。
一方で、成長投資枠での株式や投資信託の取引になると違いが出てきます。主要ネット証券5社(SBI証券・楽天証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券・松井証券)では株式売買手数料が無料となっていますが、銀行や対面型の証券会社では依然として手数料がかかるケースが多いのが現状です(プレジデント誌:新NISA口座比較)。
| 金融機関のタイプ | つみたて投資枠の購入手数料 | 成長投資枠の購入手数料・株式手数料 |
|---|---|---|
| ネット証券(大手5社) | 無料 | 無料 (株式・投信の手数料ゼロ) 出典:プレジデント誌 |
| 銀行・対面証券 | 無料(制度上) | 有料 (数百円〜数千円/1回取引) |
さらに、投資できる商品の数にも差があります。
たとえば、楽天証券の「かぶミニ®(単元未満株取引)」については2025年4月現在、2,182銘柄(リアルタイム取引対応:833銘柄)に対応しています(楽天証券プレスリリース)。
一方、SBI証券の「S株(単元未満株)」は、2024年7月時点で約3,800銘柄を扱っており、幅広い銘柄を1株から購入できます(Yahoo!ファイナンス(SBI証券比較))。
銀行の場合、単元未満株を取り扱わないことが一般的で結果的に投資先の選択肢は大幅に絞られてしまいます。
このように、同じNISA制度を利用しても、選ぶ金融機関によって投資体験に大きな差が出る点を理解しておきましょう。
月5,000円でここまで差が出る|銀行預金 vs NISA投信[5年・10年・20年の比較表]
口座乗っ取り・セキュリティ面からの比較
ここ数年、証券口座を狙った不正アクセス被害が増えています。
金融庁の調査でも2025年初頭だけで数千件の被害が確認されており、売買総額は数千億円規模に達しています。
NISA口座も例外ではなく、利用者自身のセキュリティ意識が重要です。
銀行の特徴
- 実店舗の安心感:万一不正が疑われても、窓口で直接相談できる。
- オンライン依存度が低め:手続きがややアナログで、取引スピードは遅いが不正侵入の入口は限定的。
ネット証券の特徴
- 高度な認証システム:ワンタイムパスワードや2段階認証、ログイン通知メールなどが標準化されている。
- 利便性と引き換えのリスク:オンライン完結のため便利だが、パスワード管理の甘さやフィッシング詐欺に遭うと被害に直結する。
実際の被害事例:有名投資家テスタ氏
著名な個人投資家テスタ氏も、楽天証券の口座を不正アクセスにより乗っ取られる被害に遭いました。
ウイルスソフトの二重導入や二段階認証など徹底した対策を行っていたにもかかわらず、勝手に売却注文を入れられる寸前だったといいます。
テスタ氏は自身のXで「半日気づかなければ数千万円の被害になっていたかもしれない」と語っており、厳重に管理していてもリスクはゼロにはならないことを示しています。(東京スポーツ、Rocket Boys)
まとめ
- 銀行:有人サポートで安心感があるが、取引の利便性は限定的。
- ネット証券:高度なセキュリティ機能が備わっているが、利用者の管理意識が不可欠。
どちらを選んでも不正アクセスのリスクはゼロではありません。
最終的な防御力は、利用者自身のパスワード管理・2段階認証・通知設定にかかっています。
こんな人は銀行向き/ネット証券向き
- 銀行が向いている人
- 対面で相談したい
- 投資経験がまったくなく、少額で試したい
- ネット証券が向いている人
- 手数料を抑えて効率よく資産を増やしたい
- 長期の積立投資を考えている
- 株やETFにも投資したい
体験談:私と親戚のNISA口座選び
私自身の経験
最初は地元銀行でNISAを検討しましたが、投資信託の数が限られており、魅力を感じませんでした。
最終的にSBI証券で口座を開設。投資信託の選択肢は2,000本以上あり、年間コストも大幅に抑えられています。
親戚の被害体験
一方で、親戚が証券口座を不正ログインされる被害に遭ったことがあります。
幸い、早めに気づいたため大きな損失には至りませんでしたが、勝手に株式売却の注文が入れられそうになったのです。
その後、親戚は
- ID・パスワードを定期的に変更
- 2段階認証を必ず有効化
- 取引通知メールをオンに設定
といった対策を徹底するようになりました。
実際の事例を身近で見たことで、「便利さと同時にセキュリティ管理も投資家自身の責任」だと実感しました。
ネット証券は手数料も安いし便利だけど、セキュリティ対策は自分でちゃんとやる必要があるからね。
確かに…親戚の口座が不正アクセスされた話を聞いたら、パスワードの使い回しはやめようって思いました。
FAQ
Q1. NISAの制度は銀行でもネット証券でも同じ?
制度そのものは同じです。ただし、選べる商品・手数料・サポート・操作性は大きく異なります。長期の積立や低コスト重視なら、選択肢の広いネット証券が有利なケースが多いです。
Q2. ネット証券はセキュリティ的に危ないのでは?
ネット証券は二段階認証・ワンタイムパスワード・ログイン/出金通知などシステム面の装備は強固です。
一方でオンライン完結ゆえに、パスワード管理の甘さやフィッシングなど利用者側のミスに直結しやすい側面があります。
厳重に管理していても著名投資家の不正アクセス事例があるように、リスクはゼロではありません。
対策(後述)を徹底することで実害リスクを大きく下げられます。
Q3. 銀行のほうが安全?
銀行は有人サポートや窓口があり、緊急時に直接相談できる安心感があります。
ただしオンライン取引を提供している以上、不正アクセスの可能性はゼロではない点は同じです。結論として、どちらを選んでも「利用者のセキュリティ運用」次第です。
Q4. 乗っ取りに気づいたら何をすべき?
- 口座の緊急ロック・出金停止を申請(証券会社の緊急窓口・チャット・電話)
- パスワードを即時変更(長く強い文字列/使い回し禁止)
- 二段階認証の再設定(認証アプリ・生体認証を推奨/SMSのみは回避)
- ログイン履歴と端末認証の確認(見覚えのない端末を削除)
- 注文履歴・出金履歴の精査(不正注文は速やかに問い合わせ)
- 端末のマルウェアスキャン(OS/ブラウザ/アプリのアップデート)
Q5. 具体的にどんな予防策が有効?
- 強固なパスワード(英大小字・数字・記号/20文字以上推奨/管理アプリ利用)
- 二段階認証の必須化(認証アプリ or 生体認証/バックアップコード保管)
- 公式アプリ・ブックマークのみ使用(検索経由ログインは避ける)
- ログイン・注文・出金の通知ON(異常時の即時検知)
- フィッシング対策(送信元・URL・表記の不自然さ・添付/パス付ZIPに注意)
- 公共Wi-Fiでの操作回避(やむを得ない場合はVPN)
Q6. どっちを選べばいい?(セキュリティ前提での指針)
長期の積立・低コスト・商品数ならネット証券が基本線。
ただし上記の予防策を徹底できない/対面相談が安心という人は銀行でもOK。
いずれにせよ、「二段階認証+通知+強パスワード」は最低ラインです。
まとめ:初心者は「ネット証券」が基本
NISAは銀行でもネット証券でも制度自体は同じですが、実際に投資体験に大きな差が出るのは「商品数」「手数料」「利便性」「セキュリティ管理のしやすさ」です。
- 商品数の違い:銀行は数十~数百本の投資信託が中心ですが、ネット証券は2,000本以上から選べ、株やETFも対象にできます。
- コストの違い:同じ投資信託でも、10年・20年の積立で数十万円~数百万円単位の差が生じるケースがあります。
- 利便性の違い:ネット証券ならスマホで24時間取引や確認が可能。時間の制約がある社会人にも向いています。
- セキュリティの違い:銀行は有人サポートの安心感、ネット証券は高度な二段階認証や通知機能。どちらも万能ではなく、利用者自身の管理意識が必須です。
こうした点を総合すると、長期の積立投資を効率よく続けたい初心者にとっては「ネット証券」が基本の選択肢といえます。
特に「低コスト」「豊富な選択肢」という2つの要素は、資産形成のスピードに直結するからです。
もちろん「対面で相談できる安心感」を重視する人には銀行にも価値があります。
ただし資産形成で成果を出したいなら、ネット証券を軸にし銀行は補完的に利用するという考え方が現実的です。
最後に強調すべきは、どちらを選んでもセキュリティ対策を怠らないこと。
二段階認証・パスワード管理・通知設定は、投資と同じくらい大切な「資産を守る投資行動」です。
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。
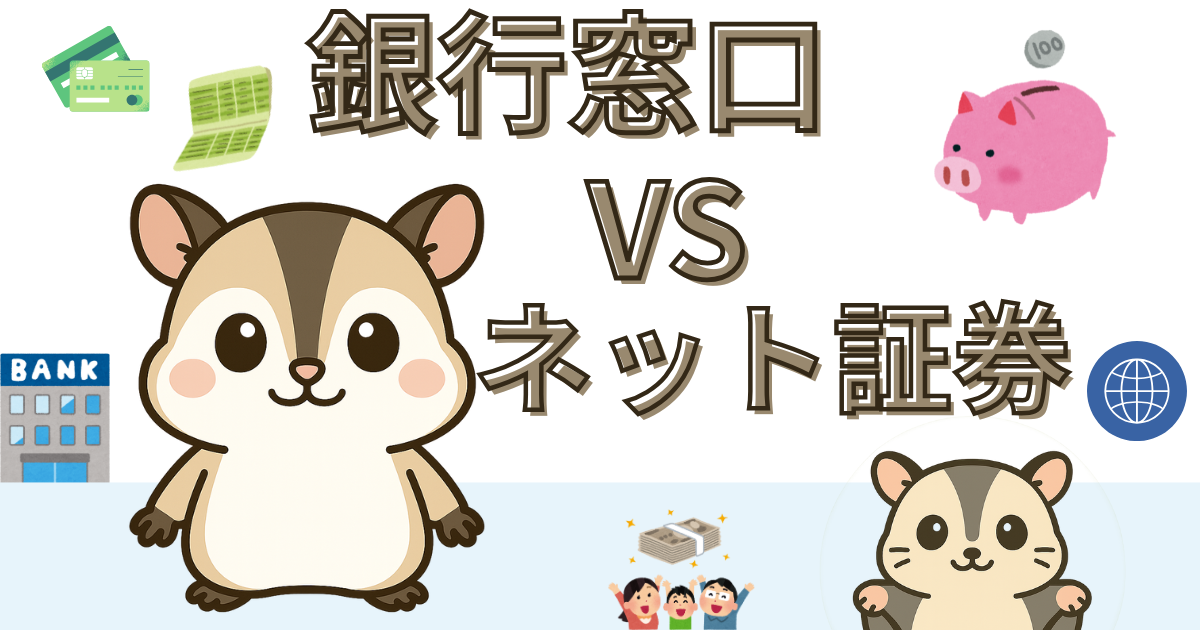

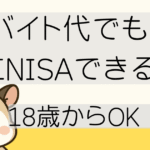
コメント