はじめに
投資信託を選ぶ前に知っておきたい基本
私が資産運用を始めたころ、一番悩んだのが「どの投資信託を選ぶか」でした。証券会社の画面には数千本もの商品が並んでいて、正直どれを選んでいいのか全くわからなかったのを覚えています。
投資信託とは、投資家から集めたお金を専門家がまとめて運用してくれる商品です。株式や債券、不動産など複数の資産に分散して投資できるため、少額でもプロの運用を活用できるのが特徴です。ただし、すべての投資信託が同じように運用されているわけではなく、手数料や投資対象の違いによって成果も大きく変わります。
そのため、投資信託を選ぶ前に「何を基準に選べばいいのか」を理解しておくことが重要です。本記事では、投資初心者でも迷わず選べるよう、ポイントを整理して解説します。
本記事で伝えたいことと活用方法
この記事でお伝えするのは、大きく分けて以下の内容です。
- 投資信託の仕組みをシンプルに理解すること
- 初心者が失敗しやすい選び方とその改善策
- 実際に筆者が選んで失敗した銘柄から学んだ教訓
- 2025年の新制度に対応した選び方の最新情報
特に「実際に失敗した投資信託」の体験談は、リアルなお金の動きや数字を交えて解説します。同じような選び方をしなければ、余計な損失を減らせるはずです。
記事を読みながら、今ご自身が保有している投資信託や、これから購入を考えている銘柄を思い浮かべていただくと理解が深まります。途中で紹介する積立投資の基礎知識や投資信託とETFの違いの記事も合わせて読めば、より具体的に選び方のイメージを持てるでしょう。
私は最初の選び方で大きく失敗した経験があるので、その失敗を繰り返さないための実践的な内容をまとめました。次の章では、投資信託の仕組みをできるだけシンプルに解説します。
投資信託の仕組みをシンプルに理解する
投資信託とはどんな仕組みなのか
投資信託は「みんなのお金をまとめて、専門家が運用する仕組み」とイメージするとわかりやすいです。例えば、私たち夫婦が毎月3万円ずつ出し合い、それをファンドマネージャーが国内外の株式や債券に振り分けて運用する、といった形です。
投資信託協会の統計によると、2024年12月末時点の投資信託の純資産総額は、公募投信246.0兆円、私募投信118.4兆円で、合計約364兆円に達しています。これは多くの個人が投資信託を活用している証拠でもあります[出典:投資信託協会・統計データ「数字で見る投資信託」]。
投資信託のメリットは次の2点です。
- 少額から幅広い資産に分散投資できる
- 運用を専門家に任せられる
ただし、運用会社ごとに方針が違うため、どんな資産にどのように投資しているかを確認することが大切です。手数料や信託報酬も商品ごとに差があり、長期的には大きな影響を及ぼします。
私自身も最初は「投資信託なら安心」と思い込みましたが、仕組みを理解せずに選んだことで失敗を経験しました。そこで次に「株式や債券との違い」を整理してみます。
株式や債券との違いを初心者向けに解説
株式は「企業に直接投資する商品」で、価格変動は大きいですが成長すればリターンも大きくなります。債券は「国や企業にお金を貸す商品」で、株式より安定的に利息を受け取れるのが特徴です。
一方、投資信託は株式や債券、不動産などをまとめて運用するため、個別株のように大きく上がることもあれば、大きく下がることもあります。ただし1つの企業だけに投資するよりリスクは分散されやすいという違いがあります。
例えば、株式に100万円投資した場合はその企業が不調なら大きな損失になりますが、投資信託を通じて50社に分散投資していれば、1社の不調が全体に与える影響は限定的です。
ここで重要なのは「投資信託=安全」ではないという点です。値動きは株式や債券と同じように市場の影響を受けるため、あくまで「リスクを分散できる商品」と理解しておくことが必要です。
投資信託は安全だと誤解する人が多いけれど、リスクがなくなるわけじゃないんだよ
なるほど!“減ることもあるけど分散でダメージを抑える”って理解すればいいんですね
私が最初につまずいたのは、この「株式や債券との違い」をあいまいに理解していた点でした。次の章では、投資信託を選ぶときに失敗しないための3つのポイントを解説します。
投資信託の選び方で大切な3つのポイント
手数料やコストを必ずチェックする
投資信託を選ぶとき、まず注目したいのが「手数料」です。購入時の販売手数料、保有中にかかる信託報酬、売却時の手数料など、見えにくいコストが積み重なります。特に信託報酬は毎年発生するため、長期投資では大きな差になります。
例えば、信託報酬が年0.3%の商品と年1.5%の商品を30年間積み立てた場合、同じ運用成果でも最終的な受取額に大きな差が生じ得ます。金融庁も「信託報酬は長期の運用成果に大きな影響を与えます」と注意喚起しています。[出典:金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック」]。
| 前提: 毎月1万円×30年 / 想定年率=5% | 値 |
|---|---|
| 最終受取額(信託報酬 0.3%) | 7,875,805円 |
| 最終受取額(信託報酬 1.5%) | 6,354,127円 |
| 差額(0.3% − 1.5%) | 1,521,678円 |
同じ運用成績でも、信託報酬が年0.3%と1.5%では30年後の最終受取額に約152万円の差が生じます。
私自身、初期に選んだ商品は信託報酬が年1.4%と高めで、10年間で運用益の多くを手数料に取られてしまいました。手数料を軽視するのは、初心者が最もやりがちな失敗のひとつだと痛感しました。
リスク分散ができるかを確認する
次に確認したいのは「どれだけ分散されているか」です。株式だけ、あるいは特定の国だけに偏った投資信託は、相場が下がったときの影響が大きくなります。
例えば、ある年に新興国株式ファンドへ集中投資していた場合、その国の景気悪化や通貨下落の影響をまともに受けてしまいます。一方、先進国株式や国内債券を組み合わせているバランス型ファンドなら、ダメージを抑えやすいです。
実際に私たち夫婦も、毎月5万円を分散型のインデックスファンドに積み立てるようにしたところ、相場が下がった年でも大きな損失を避けられました。新NISA完全ガイドや資産運用とは?をあわせて読むと、分散の効果をよりイメージできるでしょう。
過去の実績より「運用方針」を見る視点が大事
最後に大切なのは「運用方針を見る」ということです。多くの初心者が「過去の実績が良い=これからも良い」と考えてしまいますが、実際には過去の成績は将来の保証にはなりません。
例えば、直近5年間のリターンが高い商品でも、実際には特定の業種や国に偏った運用をしている場合があります。その場合、将来の環境変化によっては一気に成績が悪化するリスクがあります。
金融庁も「目先の成績にとらわれず、運用方針を確認することが大切」と明記しています[出典:金融庁「投資信託の選び方」]。ファンドの目論見書には「どんな資産にどの程度投資するのか」が必ず書かれているので、購入前に必ず確認しましょう。
私自身も、かつては実績だけで選んで痛い目を見ました。次の章では、その具体的な失敗体験を数字とともにお伝えします。
実際に失敗した投資信託から学んだこと(体験談)
選んで失敗した銘柄とその理由
私たち夫婦がかつて選んだのは「ブラジル株式ファンド」でした。2016年から月3万円を積み立て、2年間で約72万円を投じました。当時は新興国の成長に期待していたのですが、実際にはブラジル経済の不安定さや通貨レアルの下落で基準価額は下がり続けました。最終的に解約したときの評価額は約55万円。差し引き17万円の損失となりました。
失敗の理由は明確です。まず、投資対象が「ブラジル株式のみ」と極端に偏っていたこと。そして為替リスクを軽視していたことです。ブラジル経済の景気後退や政治不安で株価が下がると同時に、円高が進んだことでダブルの打撃を受けました。
さらに、信託報酬が年1.6%と高く、積み立てを続ければ続けるほどコストがかさむ構造でした。当時は「新興国は高成長だから大丈夫」と思い込んでいましたが、実際にはボラティリティが大きく、安定した資産形成には向いていなかったのです。
この経験は痛いものでしたが、今振り返ると「選び方の基準を持たずに雰囲気で決めた」ことが最大の原因だったと感じています。
その経験から気づいた投資信託選びの落とし穴
この失敗を通じて気づいたのは「投資信託=安心」ではないということでした。商品によっては、個別株と同じくらい値動きが激しく、むしろリスクが高い場合もあります。
特に初心者が陥りやすい落とし穴は次の2つです。
- 流行や話題性で選んでしまう
- コストや分散の有無を確認せずに購入する
私たちが選んだブラジル株式ファンドも、当時は証券会社のランキング上位に出ていたため「人気があるなら安心」と思ってしまいました。しかし人気=利益ではなく、むしろ過去に急騰した反動で下落することも多いのです。
また、コストを軽視したことも反省点です。信託報酬が高ければ長期で積み立てるほど手取りが減ってしまいます。投資信託は数十年単位で保有することが前提なので、わずか数%の差が大きな損失につながると実感しました。
流行りものに飛びつくのは投資の典型的な失敗パターンなんだ
確かに、人気ランキングだけで選んだら危ないんですね…
この失敗から学んだことが、今の銘柄選びの基準につながっています。次の章では、現在選んでいる投資信託の特徴をお伝えします。
現在選んでいる投資信託の特徴
今持っている銘柄の選び方
私たち夫婦が現在選んでいるのは、eMAXIS Slim 全世界株式とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2本立てです。SBI証券で口座を開設し、2021年から米国株式(S&P500)に毎月3万円を積み立てています。これに加えて、全世界株式ファンドも利用し、最初は月2万円からスタートしました。
固定費の見直し(携帯料金や保険の整理など)で支出を減らせたため、積立額を月3万円に増額。そして2025年3月からは月5万円に引き上げ、現在も継続しています。
選んだ理由は次の3点です。
- 分散性:全世界株式は数千銘柄に分散され、米国株式は世界最大の市場の成長を享受できる。
- 低コスト:どちらも信託報酬が業界最低水準で、長期投資に適している。
- シンプルさ:この2本に絞ることで、迷わず積立を続けられる。
特に全世界株式は「世界全体の平均点を取る」考え方で、S&P500は「成長の中心である米国に厚みを持たせる」役割として位置づけています。投資信託とは?や新NISA完全ガイドも合わせて読むと理解が深まるでしょう。
以前の失敗と比べて改善したポイント
以前のブラジル株式ファンドの失敗では、「人気ランキングに惑わされて偏った商品を選んだ」ことが原因でした。その経験を踏まえ、今は分散・低コスト・長期積立の3つを軸にしています。
改善した点は次の通りです。
- 流行で選ばない:一時的な話題性ではなく、長期的に持てる商品を選ぶ。
- コストを重視:信託報酬0.1%未満のインデックス型に絞った。
- 積立額を段階的に増やす:最初は無理せず2万円、支出削減後に3万円、さらに固定費を削ったうえで5万円と、生活に合わせて増額。
結果として、2021年からのS&P500積立と、2023年以降の全世界株式積立の両方で資産が順調に増えています。2025年9月時点、この2銘柄で投資総額約450万円に対し、評価額は520万円を超えました。
こうして「焦らず、確実に積み立てる」姿勢を持てるようになったのは、過去の失敗があったからこそです。
次の章では、2025年の制度変更を踏まえた投資信託選びのポイントを紹介します。
最新の制度変更や動向を踏まえた選び方
2025年の新NISA・制度改正のポイント
夫婦共働き・子どもなしの私たちも、2025年の新NISA制度を調べて「これなら使える」と感じた変更がありました。理解に苦労した点も多かったですが、落ち着いて整理したので共有します。
主な制度改正ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| つみたて投資枠と成長投資枠の併用 | 旧制度では「つみたてNISA」と「一般NISA(現 成長投資枠)」のどちらかを選ぶかだったのが、2024年からは両方を使えるようになっています。これにより戦略の幅が広がりました。 |
| 年間非課税投資枠の拡大 | 年間で使える非課税枠が「つみたて投資枠:120万円」「成長投資枠:240万円」、合計最大360万円になりました。旧制度に比べて資金をより積極的に運用しやすくなっています。 |
| 非課税保有限度額(生涯枠)の引き上げ | 新NISAでは、生涯にわたって非課税で投資できる「総額枠」が1,800万円に設定され、そのうち成長投資枠で使えるのは最大1,200万円までという制限があります。 |
| 非課税保有期間が無期限に | 従来は“つみたてNISAで20年”、“一般NISAで5年”といった期間制限がありましたが、新制度では保有期間の制限がなくなり、売却しない限り非課税で保有可能です。長期での資産形成に適しています。 |
| 売却による非課税枠再利用の可能性 | 投資信託などを売却した際、その分の「簿価(取得金額)」が翌年以降に非課税枠として復活する制度になっています。ポートフォリオの入れ替えなど戦略をとる際に有利です。 |
注意すべき点・最新動向
- 成長投資枠での利用可能商品の範囲が広がっていますが、毎月分配型など“高頻度分配型”の商品については依然、慎重な姿勢です。手数料や分配の仕組みをよく確認する必要があります。
- 年間投資枠を使い切れなかった分の“繰り越し”はできません。例えば、成長投資枠240万円のうち100万円しか使わなかったからといって、翌年にその分を使えるわけではないことに注意。
- 生涯枠1,800万円を意識した使い方が求められます。特に成長投資枠1,200万円の制限があるため、どの枠にどれだけ配分するか戦略をもっておくことが重要です。
- 制度は比較的新しく、今後の税制改正要望で商品対象の拡充や未成年の利用拡大などが提案されています。最新情報を常に確認することが必要です。
初心者が知っておきたい最新の投資信託トレンド
私自身、以前の失敗から学び、「ただ利回りが良い」と言われるものではなく制度やトレンドを意識して選ぶようになりました。以下は今注目しているトレンドです。
今のトレンド・選び方で注目している点
- 全世界株式インデックス型の人気上昇
国や地域を限定せず世界株式を幅広く追うタイプのファンドが成長投資枠・つみたて投資枠両方で人気があります。分散性が高いのでリスクが一国依存になりにくい。
日本証券業協会の調査では、新NISA利用者のうち、つみたて投資枠では「投資信託(インデックス型)で全世界株式(日本を含む)」が最も多く選ばれているタイプであることが確認されています。 出典:日本証券業協会 - 低コスト・信託報酬のより低い商品を選ぶ傾向
手数料が小さいことがより一層重視されており、「Slim」「たわらノーロード」など低コストインデックス型ブランドの信頼が高くなっています。ランキングでも信託報酬0.1%前後のものが上位に来ることが多いです。 出典:みんかぶ(投資信託) - 非課税枠を最大限活用した分散戦略
新NISAでは年間枠と生涯枠が大きいため、枠をどう使うか計画を立てておく人が増えています。つみたて枠と成長枠を組み合わせて、国内株式、先進国株式、全世界株式など複数のインデックス商品をポートフォリオに含めるケースが多いです。
よくある質問(FAQ)
投資信託は少額からでも始められる?
はい、投資信託は1,000円程度から購入できるものも多くあります。証券会社やネット証券では「100円から積立可能」という商品も増えており、少額からコツコツ積み立てられるのが魅力です。
例えば私たち夫婦は、最初は毎月1万円ずつ積み立てて様子を見ました。慣れてきたところで3万円、5万円と増額し、現在は毎月5万円を続けています。最初から無理をせず、自分の生活に合った金額で始めることが長続きのコツです。
金融庁も「少額から分散投資をすることが長期的な資産形成に効果的」と強調しています[出典:金融庁「つみたてNISAの概要」]。また、100円単位で積立できるサービスを利用すれば、投資を「習慣化」しやすいのもメリットです。
どのくらいの期間で成果を見込むべき?
投資信託は短期で利益を狙う商品ではありません。一般的に5年〜10年、できれば20年以上の長期を見据えて取り組むことが大切です。
理由は、短期的には相場の上下に左右されやすいからです。例えば株式市場は1年の間に10〜20%の上下がよくあります。しかし、長期で積立を続けると「安いときに多く買える」効果(ドルコスト平均法)が働き、結果としてリターンが安定しやすくなります。
私たち夫婦も、5年間で資産評価額が約70万円増えましたが、それは「焦らず毎月同じ額を積立て続けた」ことが理由です。長期投資のメリットやつみたて投資の効果を読んでいただくと、具体的なイメージが湧きやすいと思います。
次はまとめとして、失敗から学んだポイントを整理します。
まとめ
失敗から学んだ投資信託選びのポイント整理
ここまで解説してきた内容を整理すると、投資信託を選ぶ際に大切なのは次の3つでした。
- 手数料やコストを確認すること
└ 信託報酬が高い商品は長期で大きな差を生む。 - 分散投資ができているかをチェックすること
└ 特定の国や業種に偏るとリスクが高まる。 - 過去の成績より運用方針を重視すること
└ ランキングや流行で判断しない。
私たち夫婦はブラジル株式ファンドで約17万円の損失を経験しましたが、それをきっかけに「世界全体に低コストで投資できる商品」に切り替えました。その結果、安定して資産が増えています。
投資信託は数が多く迷いやすいですが、選び方の基準を持つことで失敗を減らせると実感しています。
長期的な視点で投資を続ける大切さ
最後に一番伝えたいのは「焦らず続けること」です。投資信託は短期で成果を出すものではなく、10年・20年と積み立ててこそ効果が出ます。
私たちは2021年から毎月3万円で積立を開始し、2025年3月からは月5万円にしました。段階的に無理なく続けた結果、2025年9月時点の評価益は約70万円。一発狙いではなく、コツコツ積み立てた成果です。
金融庁も「長期・積立・分散」が資産形成の基本と強調しています[出典:金融庁「資産形成の基本」]。
投資は短距離走じゃなくてマラソンなんだよ
なるほど!長く続けることが成功の一番の近道なんですね
この記事を通じて、投資信託選びの失敗を繰り返さないための基準を持ち、安心して長期投資を続けるきっかけになれば嬉しいです。
投資に関する免責事項
本記事の情報について
本記事では、投資信託の仕組みや選び方、筆者自身の体験談をもとに解説しました。ただし、ここで紹介している情報は一般的な知識の提供を目的としたものであり、特定の商品を推奨するものではありません。
記載内容は2025年9月時点での制度・金融庁の公開データ・証券会社の情報をもとにしていますが、制度改正や市場環境の変化によって今後内容が変わる可能性があります。投資を検討される場合は、最新の公的情報や証券会社の公式サイトで必ず確認してください。
投資判断はご自身の責任で行ってください
投資信託を含む金融商品は、元本保証がなく、運用成績によっては損失が発生する場合があります。特に株式や新興国資産に投資するファンドは、価格変動や為替リスクの影響を大きく受けることがあります。
本記事で紹介した体験談も、あくまで私自身の事例であり、すべての人に当てはまるわけではありません。読者の方それぞれの収入・支出・ライフプランによって最適な投資方法は異なります。
したがって、投資の最終判断は必ずご自身の責任において行ってください。証券会社の担当者やファイナンシャルプランナーに相談することも検討すると安心です。
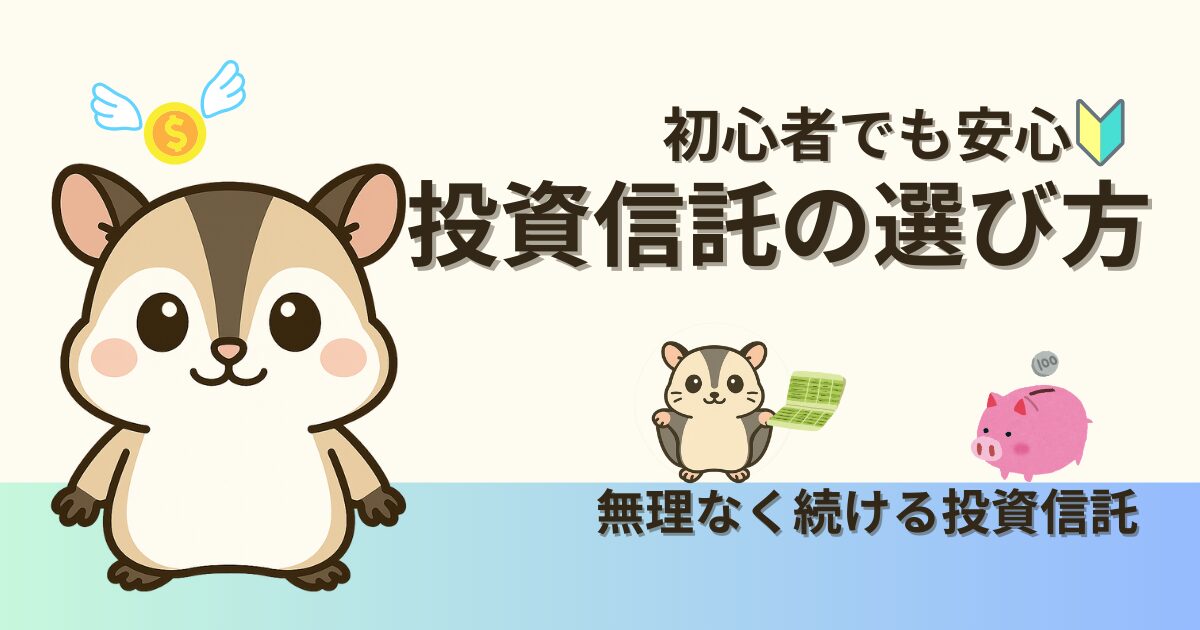


コメント