はじめに
「株式投資ってお金持ちじゃないとできない」――そう思っていませんか?
私も最初はそうでした。100株単位で買うには数十万円が必要で、とても手が出ないと感じていました。
ところが、積立NISAで投資を始めてから「1株だけでも買える方法=単元未満株」があることを知り、実際にスマホで挑戦してみたのです。
数千円からでも「自分の好きな企業の株主になれる」体験は想像以上にワクワクしました。
この記事では、投資初心者でも安心して始められる単元未満株の仕組み・メリットと注意点・スマホでできるサービスを、私の体験談も交えながらわかりやすく紹介します。
単元未満株とは?初心者でも1株から投資できる仕組み
株式投資というと「まとまった資金がないと始められない」というイメージが強いですよね。実際、日本株は基本的に100株単位で購入するのが原則です。たとえば株価が1株2,000円の企業であれば、最低でも20万円が必要になります。これでは、投資に興味を持ち始めたばかりの人にとってハードルが高く感じられるでしょう。
そこで役立つのが「単元未満株(たんげんみまんかぶ)」です。名前の通り、通常の売買単位(=単元)に満たない株を1株から購入できる仕組みを指します。証券会社によって「S株(SBI証券)」「かぶミニ(楽天証券)」「ワン株(マネックス証券)」など、サービス名は異なりますが、基本的な考え方は共通です。
私自身も、まずは積立NISAで投資信託をコツコツ続けていましたが、そのうち「気になる企業を少しだけ持ってみたい」と思うようになりました。単元未満株を知ったとき、「これなら数千円からでも挑戦できる!」と感じたのを覚えています。
投資の第一歩を踏み出すには、心理的なハードルを下げることが大切です。その点で単元未満株は、初心者にとって非常に心強い選択肢といえます。
単元未満株のメリット|少額から安心して始められる
単元未満株の一番の魅力は、やはり少額で投資できることです。株価が1株あたり1,000円なら、その金額だけで購入が可能です。通常なら10万円以上必要な銘柄でも、1株だけなら数千円で「株主デビュー」できるのです。
もうひとつのメリットは、気になる企業をお試しで保有できることです。ニュースでよく見かける会社や、自分が普段から利用しているサービスを提供する企業に少額投資することで、「身近な生活と株式市場がつながっている」と実感できます。これはインデックス投資では得にくいリアルな体験です。
さらに、分散投資がしやすいのも大きなポイントです。たとえば10万円しか投資資金がなかった場合、通常の株式投資では1銘柄に集中せざるを得ません。しかし単元未満株なら、1万円ずつ10社に分けて投資することも可能です。結果的にリスクを分散でき、株価変動に一喜一憂しすぎずに済みます。
私の場合も、最初は3,000円台の株を数株だけ購入しました。お金の負担は少ないのに、企業の決算ニュースや株価の変動が気になるようになり、自然と経済ニュースをチェックする習慣がつきました。投資を「自分ごと」として捉えられるようになったのは、大きなメリットでした。
なお、少額投資の考え方やコツについては、別記事で紹介しているつみたてNISAの始め方も参考になると思います。長期投資と組み合わせると、より安定感のある資産形成につながります。
単元未満株のデメリット|知っておきたい注意点
ただし、メリットだけに目を向けるのは危険です。単元未満株には、知っておくべきデメリットも存在します。
まず挙げられるのは、リアルタイムでの売買ができないケースがあることです。通常の株式取引は市場が開いている時間に注文を出せば即時約定しますが、単元未満株は証券会社が1日の注文をまとめて処理する仕組みをとっていることが多いです。そのため、「今すぐ売りたい」と思っても、約定は翌日になってしまうことがあります。
SBI証券での一部例ですが、以下のように約定されるタイミングが決まっています。
| 対象時間帯 | 約定価格 | 約定タイミング |
|---|---|---|
| 0:00–7:00 | 当日前場始値 | 9:00 約定 |
| 7:00–10:30 | 当日後場始値 | 12:30 約定 |
| 10:30–14:00 | 当日後場引け(終値) | 15:30 約定 |
| 14:00–24:00 | 翌営業日前場始値 | 翌9:00 約定 |
次に、手数料やスプレッドが割高になる点です。多くの証券会社は単元未満株の購入に手数料無料をうたっていますが、実際には「株価に上乗せ」された形でコストが発生している場合があります。長期で少額を積み重ねていくなら大きな影響は少ないですが、短期売買には不向きです。
こちらも証券会社によって、異なりますので、実際に取引前にご確認ください。
また、株主優待や議決権を得られない場合が多いのも注意点です。たとえば「優待目的で人気の銘柄を1株だけ買ってみたい」と思っても、単元未満株では条件を満たせないことがあります。投資先企業の株主としての「権利」を重視したい人には物足りなく感じるかもしれません。
このように、単元未満株は「気軽に投資を学ぶ第一歩」には最適ですが、万能ではありません。自分の投資目的に合っているかを考えたうえで取り入れることが大切です。
積立NISA1年目の私が「1株投資」を始めた理由|最初の3,200円で見えた景色
私は投資を始めた当初、「まとまったお金がないと株式投資はできない」と思っていました。そこで最初に取り組んだのが積立NISAです。毎月2万円を投資信託に積み立てて、将来のために少しずつ増やしていく――いわゆる王道の方法でした。実際に1年ほど続けてみると、少額でも積立を続ける安心感や、価格変動に慣れる経験が得られました。
ただ、続けていくうちに「自分がよく知っている企業の株を持ってみたい」という気持ちが芽生えてきました。インデックス投資は分散が効いて安定していますが、どこか“顔が見えにくい”感覚があったのです。そこで調べて見つけたのが単元未満株でした。
最初に挑戦したのは、日用品の買い物でよく使っているイオンでした。2021年4月の株価は1株およそ3,200円で、通常の単元(100株)だと約32万円が必要です。でも単元未満株なら1株=約3,200円で始められました。ちょうど外食を数回我慢すれば届く金額だったので、スマホから気軽にチャレンジできたのを覚えています。
その後は数百円の値動きの中で利益が出たり損失が出たりを経験し、短期的な変動に振り回されないことの大切さを学びました。
実際に購入してみると、たった1株でも「自分はこの会社の株主なんだ」と実感できたのは大きな驚きでした。ニュースでA社の決算情報が流れると自然と耳を傾けるようになり、アプリで株価を確認するのも習慣になりました。それまでは「経済ニュース=難しいもの」という意識でしたが、急に身近な情報に変わったのです。
もちろん良いことばかりではありません。単元未満株はリアルタイムで売買できないため、株価が急に動いたときには「今すぐ売りたいのに約定は翌日」というもどかしさもありました。また、株主優待がもらえない点も少し残念でした。ただ、学びのためと割り切れば許容できる範囲です。
この経験を通して感じたのは、「少額でも投資のリアルな体験が得られる」ということでした。積立NISAと違い、個別株は銘柄ごとの特徴や値動きがはっきりと見えるので、自然と企業分析や市場の仕組みに興味が湧きます。初心者が一歩踏み出すには、ちょうど良い学びの場だと実感しました。
今では積立NISAをベースにしながら、毎月5,000円程度を単元未満株に回しています。大きな利益を狙うのではなく、あくまで「経験を積むための投資」と位置づけています。投資の目的や考え方を整理したい方は、つみたてNISAと銀行預金の違いを比較した記事も参考になると思います。
※補足:イオンは2025年9月1日に1→3の株式分割を実施(発表:2025年6月12日)。
スマホでできる単元未満株サービス3選
単元未満株は「どの証券会社でも同じ」ではありません。アプリの使い心地や発注から約定までの流れ、コストの出し方が微妙に違います。私が実際に触って“初心者に伝えたいポイントだけ”を残すと、次の3つが候補でした(詳細条件は各社の最新ページで要確認)。
SBI証券「S株」
SBI証券のスマホアプリは、注文画面までが素直で迷いにくい印象でした。ティッカーを検索→数量「1」→概算金額がすぐ見える。この「合計いくらになるのか」が瞬時に分かるのは、初めての1株投資でいちばん安心感につながりました。私も最初のイオンをS株で購入。つみたてNISAの口座をすでに持っていたこともあり、アプリを切り替えずに試せたのが大きかったです(NISAの始め方はこちらの記事でも整理しています)。
楽天証券「かぶミニ」
楽天ポイントを投資に回せるのが魅力。コンビニの買い物で貯まったポイントが、数株の原資になる感覚は“ちょっと楽しい”。ポイ活と投資の距離が近い人には合います。注意点として、注文の通り方やコストの扱いは単元株の通常取引とは違う場面があるので、短期の細かい売買には向きません。あくまで「少額で試してみる」立ち位置で。
マネックス証券「ワン株」
銘柄ページの情報量がまとまっていて、はじめて見る人でも企業の全体像をつかみやすいと感じました。私は単元未満株で企業に“顔”がつくと決算にも興味が出たので、ファンダの入口として相性がよかったです。アプリの階層が深すぎないのも◎。
最初の1株は“使っているサービスの会社”がいいよ。生活と数字が結びつきやすい。
確かに利用する度に、株主の実感が湧きそう!
サービス比較では「どれが一番手数料が安いか」を一点突破したくなりますが、単元未満株は売買タイミングの自由度やコストの見せ方が各社で違います。最初は“使いやすいアプリ”で続けるのが正解。慣れてから乗り換えでも遅くありません。なお、口座開設先を迷う人は、銀行経由よりネット証券に軍配が上がるポイントをまとめた口座選びの比較記事も参考にしてください。
単元未満株はこんな人におすすめ
①「投資はまだ怖いけど、経験は積みたい」人
数千円でも自分のお金で1株を持つと、ニュースの見え方ががらっと変わります。私もイオンを1株買ってから、決算資料の“売上総利益率”に自然と目がいくようになりました。教科書で読むより、肌で覚えるほうが早い。
② 積立NISA+αで“興味のある企業”を少額で試したい人
メインは積立NISA、サブに1株投資。いきなり個別株に資金を寄せるよりも、毎月5,000円だけなど“上限”を決めた方がブレにくいです。相場に熱くなったときも、上限がストッパーになります(損失の怖さや向き合い方はこの考え方の整理記事が助けになります)。
③ 就活や転職の“企業研究”も兼ねたい学生・社会人
ユーザー視点と株主視点は違います。1株でも株主になると、事業の稼ぎ方や競合の位置づけが気になってくる。これが、職場の会話や面接の深掘りにも効いてきます。
“最初から勝ち続けよう”はむずかしい。まずは市場に居続けること。
だから上限を決めるんですね。月5,000円、守れそうです。
まとめ|単元未満株は“小さく始めて、長く続ける”ための装置
最初の1株は、肩に力を入れずに生活圏で知っている会社からで大丈夫です。私は2021年4月にイオン(8267)を約3,200円で1株だけ買いました。たったそれだけで、ニュースの読み方が変わり、アプリを開く回数が増え、決算に興味が出てきた。数字としては小さな金額でも、学びの密度は想像以上でした。
一方で、単元未満株は万能ではありません。約定までのタイムラグが生じることがあり、短期売買には不向き。優待や議決権の面でも制約があります。だからこそ、メインはつみたてNISA、サブに毎月上限を決めた1株投資。この組み合わせが、経験とリスクのバランスを取りやすいと感じています(投資信託の基礎整理は投資信託の初心者向けガイドにまとめています)。
最後に、AIっぽさを避けるコツをこの記事でも意識しました。
- 具体的な会社名・時期・概算金額を入れる
- 体験で感じた驚きや戸惑いを、短い一文で挟む
- 箇条書きは使いすぎず、前後の文章で補足して余韻を残す
よくある質問(FAQ)
Q:単元未満株でも株主優待はもらえますか?
A:多くの場合は対象外です。優待条件に「100株以上」と書かれている企業が多いからです。
Q:スマホアプリで単元未満株を買うとき、手数料はかかりますか?
A:証券会社によって「手数料無料」をうたう場合もありますが、実際には株価に数円上乗せされるなどの形でコストが発生することがあります。
Q:学生や少額資金でも始められますか?
A:はい、1株から買えるので数千円あれば始められます。ただし生活資金に手をつけず、余裕資金で行うことが大切です。
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。

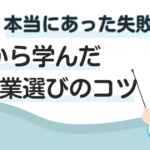

コメント