はじめに
投資を始めた頃、カタカナや専門用語がわからなくて何度も検索した経験はありませんか?
私も「インデックスって何?」「分配金って配当と違うの?」と混乱していました。
そこで本記事では、私が初心者として調べまくった投資用語10選(PART2)をまとめました。実際に投資を始めてから「あのとき知っておけば楽だった!」と感じたワードを中心に、やさしく解説します。
投資商品の種類を知ろう
インデックスファンド
インデックスファンドは「市場全体の平均」に連動する投資信託です。
例:日経平均株価やS&P500に合わせて運用されます。
初心者に人気の理由は、個別株を選ばなくても市場全体に投資できる安心感があるからです。
私自身も最初はインデックスファンドに毎月5,000円ずつ積み立て、1年後にはプラス7,800円の利益が出ました。
値動きはありますが、ゆるやかに資産が増える感覚を持てました。
以下がインデックスファンドの例になります。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
→ S&P500に連動。低コストで超定番。 - eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
→ 1本で全世界に分散できる人気商品。 - SBI・Vシリーズ(SBI・V・S&P500など)
→ バンガードETFを原資にした低コストファンド。 - ニッセイ外国株式インデックスファンド
→ 日本を除く先進国株に投資。老舗で安定感あり。 - 楽天・オールカントリー株式インデックスファンド
→ 楽天投信の全世界株ファンド。
投資信託の選び方【2025年版】では初心者向けに選び方を解説しています。
アクティブファンド
アクティブファンドは、運用のプロが銘柄を選んで「平均を上回るリターン」を目指す投資信託です。
ただし信託報酬(運用コスト)が高めです。
私は一度、信託報酬が年1.5%のファンドに投資しましたが、結局はインデックスと大差が出ず「コストが重い」と実感しました。
- ひふみ投信/ひふみプラス(レオス・キャピタルワークス)
→ 「顔が見える運用」で有名。テレビやでもよく紹介され、初心者にも認知度が高い。 - ジェイリバイブ(Jリバイブ)シリーズ(SBIアセットマネジメント)
→ 成長期待の中小型株に集中投資。積立NISAの対象外ですが、コアな人気あり。 - アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信(AB米国成長株)
→ 米国グロース株に積極投資。分配金型が人気で、販売額ランキング上位常連。 - フィデリティ・USリート・ファンド
→ 米国の不動産に投資。分配金狙いの投資家に長年人気。 - コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
→ 長期的に成長する30銘柄を厳選。社会的責任投資(ESG)の観点からも注目。
| 観点 | インデックス | アクティブ |
|---|---|---|
| 目標 | 市場平均に連動 | 平均超えを狙う |
| コスト | 低コスト | 高め |
| 値動きの安定性 | おおむね安定(市場平均と同じ動き) | 成績が大きく上下する場合あり |
| 選び方 | 指数・コストで比較 | 運用方針・実績・コストを総合比較 |
ETF(上場投資信託)
ETFは「投資信託の仕組みを持ちながら、株式のように市場で売買できる商品」です。
通常の投資信託は1日1回の基準価額でしか売買できませんが、ETFは株と同じくリアルタイムで値段が動くため、売買の自由度が高いのが特徴です。
例えば「東証ETF」には日経平均株価やTOPIXに連動するもの、米国市場ではS&P500やNASDAQ100に連動するものなどが多数上場しています。
私も楽天証券で「S&P500連動ETF」を買いましたが、1口が約2,000円から購入できたので、投資信託と比べても手軽さを実感しました。
REIT(不動産投資信託)
REIT(リート)は「不動産に投資できる投資信託」です。
投資家から集めたお金でオフィスビルや商業施設、マンションなどを購入・運用し、その収益(家賃収入など)を分配金として投資家に還元します。
たとえば J-REIT(日本のREIT) には、東京のオフィスビルや大型ショッピングモールを保有しているファンドがあります。これを買うと「間接的にその不動産のオーナーの一部」になれるイメージです。
メリットは、不動産を1棟まるごと買うのは数千万円かかるところを、REITなら数万円から投資できる点です。また、複数の物件に分散投資されているため、1つの物件の空室リスクが軽減されます。
一方で、REITの価格は 不動産市況や金利の動向に影響を受けやすい ため、分配金が安定しているからといって「完全に安全」というわけではありません。
債券
債券は「国や企業にお金を貸して、その利息を受け取る」金融商品です。株式のように大きく値動きするわけではなく、満期まで持てばあらかじめ決まった金利が得られる点が特徴です。
例えば「個人向け国債」は1万円から購入でき、利息が保証されています。私も資産の一部を3年満期の国債に入れたことがありますが、相場が荒れて株がマイナスになったときも、利息が確実に入ってきたことで精神的に安心できました。
ただしデメリットもあり、金利が上がると既に保有している債券の価値は下がります。そのため「安全資産」とはいえ、完全にリスクゼロではないことを知っておくのが大切です。
| 商品 | 特徴 | コスト | 注意点 |
|---|---|---|---|
| インデックスファンド | 市場平均をまるごと | 低 | 短期で大きく増やすのは苦手 |
| アクティブファンド | プロが選んで上振れ狙い | やや高め | 当たり外れ・ブレ大 |
| ETF | 上場投資信託。株のように売買できる | 低 | 売買コストやスプレッドに注意 |
| REIT | 不動産の家賃収益を分配 | 中 | 金利・市況の影響 |
| 債券 | 利息で守りを固める | 低〜中 | 金利上昇で価格下落 |
投資の方法・仕組み
単元未満株
通常の株式投資は「100株単位」での購入が基本です。例えば1株2,400円だとしても、100株で24万円必要になります。
でも「単元未満株」なら1株から買えるので、私も最初に某企業の1株だけ(当時232円)購入しました。小額でも株主になれたのが楽しくて、学びにつながりました。
| 項目 | 単元未満株 | 通常取引(単元株) |
|---|---|---|
| 最低購入金額 | 1株からOK(少額) | 100株が基本(銘柄により異なる) |
| 注文の約定タイミング | リアルタイムでない場合あり | 市場の板で即時約定可 |
| 手数料 | 証券会社ごとにルールあり | 通常の売買手数料 |
| 配当の受取 | 受け取れる(按分) | 受け取れる |
| 株主優待 | 対象外のことが多い | 条件を満たせば対象 |
ドルコスト平均法
ドルコスト平均法は「毎月同じ金額で積み立てる」方法です。株価が高いときは少なく、安いときは多く買うことで、購入価格が平均化されます。
私は過去月1万円を投資信託に積み立てていましたが、2022年の下落相場でも「安く仕込めている」と前向きに考えられました。心理的な安心感が大きなメリットです。
積立NISAはまさにドルコスト平均法を活用した投資手法です。
積立NISAの始め方【2025年最新版】
NISAは銀行?ネット証券?初心者が迷わない口座開設の選び方
| 月 | 基準価額 | 拠出額 | 購入口数 | 累計口数 | 平均取得単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 10,000 | 1.000口 | 1.000口 | 10,000 |
| 2 | 8,000 | 10,000 | 1.250口 | 2.250口 | 8,889 |
| 3 | 12,000 | 10,000 | 0.833口 | 3.083口 | 9,734 |
| 4 | 9,000 | 10,000 | 1.111口 | 4.194口 | 9,549 |
| 5 | 11,000 | 10,000 | 0.909口 | 5.103口 | 9,784 |
| 6 | 10,500 | 10,000 | 0.952口 | 6.055口 | 9,917 |
| ※ 平均取得単価 = 累計拠出額 ÷ 累計口数(概算)。数値は説明用の例です。 | |||||
投資のリターン・指標
分配金
投資信託やREITから支払われるお金です。似ている用語に「配当」がありますが、配当は企業が株主に渡す利益の一部。分配金は投資信託の運用成果から支払われます。
私は毎月分配型ファンドを買ったことがありますが、実際は元本を削って分配しているケースもあり、注意が必要と学びました。
| 項目 | 分配金(投資信託/REIT) | 配当(株式) |
|---|---|---|
| 支払い元 | ファンドの運用収益 | 企業が稼いだ利益 |
| 原資 | 収益+場合により元本払い戻しを含む | 主に当期純利益 |
| 頻度 | 月次/年数回など商品ごと | 年1〜2回が多い(企業による) |
| 投資家の注意点 | 「高分配=高リターン」とは限らない | 配当性向が極端に高いと将来投資が細る懸念 |
配当性向
配当性向は「会社が稼いだ利益のうち、どれくらいを株主に配当で渡しているか」を示す割合です。
例えば利益100億円で配当30億円なら配当性向30%。高ければ株主に還元している姿勢が強いですが、100%に近いと「内部留保が少なく、将来の投資余力が不安」という見方もされます。
| 項目 | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| 当期純利益 | 100億円 | 会社が最終的に稼いだ利益 |
| 配当総額 | 30億円 | 株主に配る合計金額 |
| 配当性向 | 30% | =30 ÷ 100 × 100 |
30〜50%:配当と成長投資のバランスが取りやすい
70%超:株主還元は厚いが、将来投資の余力がやや心配な場合も
日経平均先物
「将来の日経平均株価をいくらにするか」を取引する商品です。
現物の株を受け渡しするのではなく、価格差のやり取りが基本。機関投資家や短期売買の参加者が値動きに備えるヘッジや短期戦略で使います。
私は先物取引に手を出したことはありませんが、ニュースで「先物が下がった」と報じられると、翌日の株式市場にも影響が出ます。
初心者は仕組みを理解しておくだけで十分です。
まとめ
今回は「インデックスファンド・ETF・REIT・単元未満株・ドルコスト平均法」など、実際の投資でよく目にする用語を解説しました。
用語を一度で完璧に覚える必要はありません。投資を続けるうちに自然と身につきます。
まずは 自分が使う可能性のある用語 から理解していきましょう。
前回の初心者向け用語解説PART1と合わせて読むと、さらに理解が深まります。
関連記事
投資に関する免責事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。

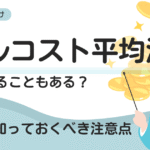
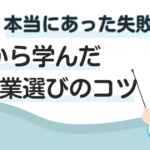
コメント