はじめに
ドルコスト平均法は「投資初心者に安心」とよく紹介される方法ですが、実際にはメリットだけではなくデメリットも存在します。特に積立を始めたばかりの人にとっては「本当に損しないの?」「失敗例はあるの?」と不安に思うこともあるでしょう。
この記事では、仕組み・メリット・リスクをわかりやすく解説し、初心者が注意すべき点を体験談も交えて紹介します。
ドルコスト平均法とは?
ドルコスト平均法とは、価格が変動する金融商品に対して「一定額を定期的に投資する方法」のことです。
たとえば毎月1万円を投資信託に積み立てる、といった形が代表的です。
この方法の特徴は、価格が高いときには少ししか買えず、価格が安いときには多く買えるという点です。結果として平均購入価格をならし、長期的にリスクを抑えられる仕組みとされています。
| 月 | 価格(円/個) | 毎月の予算(円) | 購入個数(個) | その月の購入量 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | |
| 2月 | 500 | 1,000 | 2.0 | |
| 3月 | 2,000 | 1,000 | 0.5 | |
| 合計 | — | 3,000 | 3.5 | |
| 評価 | 現在価格:2,000円/個 | 保有価値 | 3.5個 × 2,000円 = 7,000円 | |
ドルコスト平均法は投資信託や積立NISAなど、初心者が利用しやすい制度でもよく使われています。
個別株の場合は購入時にそもそも値段の変動があるため、積立NISAにぴったりの手法です。
積立NISAの始め方|初心者でも簡単にできるやり方【2025年最新版】
ドルコスト平均法のメリット
価格変動リスクを分散できる
投資でもっとも難しいのは「いつ買うか」を正確に当てることです。相場は日々上下し、プロでも完全に予測するのは不可能といわれています。
ドルコスト平均法では、毎月(あるいは毎日)一定額を投資するため、購入価格が自然にばらけます。高値でまとめて買ってしまうリスクを抑えられ、平均購入単価が安定しやすくなります。
たとえば、毎月1万円を積み立てて価格が「1000円 → 500円 → 2000円」と変動した場合、合計3万円で3.5口を購入できます。このとき平均購入単価は約857円。結果的に「高いときは少なく、安いときは多く」買えたことになります。
投資のタイミングを考えなくていい
相場の値動きを気にして「今が買い時かな?」「もう少し待つべきか?」と迷うのは、多くの初心者が感じるストレスです。ドルコスト平均法では毎月自動的に買い付けを行うため、投資の判断をその都度下す必要がありません。
これは心理的なメリットも大きく、「欲に駆られて高値で買う」「恐怖で安値を逃す」といった感情に左右されにくくなります。初心者にとっては“続けやすい仕組み”そのものが安心材料となります。
少額からコツコツ始められる
「投資=まとまったお金が必要」と思われがちですが、ドルコスト平均法を活用すれば、100円や1,000円といった少額からでも始められます。証券会社によってはクレジットカード決済で毎月自動積立ができるサービスもあり、家計のなかで無理のない範囲で続けられます。
少額でも長く続けることで複利の効果が働き、気付いたときには大きな資産になっていることがあります。たとえば月5,000円を20年間積み立て、年3%の利回りで運用すると元本120万円に対し、約164万円まで増える計算になります。
ここまで聞いただけだとメリットしかないけど大丈夫?
いい事だけ聞くと飛びついてしまうよね。だから次にデメリットを解説するよ。
ドルコスト平均法のデメリット・リスク
一方で、初心者にとって見落としがちな注意点もあります。
長期でも必ず利益が出るわけではない
ドルコスト平均法は“購入タイミングの分散”で価格変動のブレをならす方法です。値動きそのものを好転させる魔法ではありません。
たとえば投資対象の実力(企業収益や指数の構成)が伸び悩み10年スパンで基準価額が横ばい〜緩やかな下落にとどまった場合、積立を続けても評価額が元本付近で停滞することはあります。
また、信託報酬(手数料)が高い商品だとリターンがさらに削られます。
積立の仕組みが良くても、投資対象の成長力とコストが伴わなければ成果は出にくい、というイメージです。
例:信託報酬0.6%のアクティブ型と0.1%のインデックス型を10年で比較すると10年で約5%分のパフォーマンス差になり得ます。
積立と相性が良いのはコストが低く、長期で分散が効いた商品です。
投資信託の選び方|初心者が失敗しない3つのポイント【2025年版】
下落相場が長引けば含み損が続く
“安いときに多く買える”のは事実ですが、下落が長く続くほど平均取得単価もじわじわ下がるため、評価益へ転じるまで時間がかかります。
とくに、目標期間が短い(3〜5年)のに価格が戻らないケースでは、評価損のまま終了する可能性が現実的にあります。
例:毎月1万円を3年(36万円)積立。価格が初期100→最安70→最終85で終わった場合、取得単価は下がるものの終値85が平均取得単価を上回らなければ含み損です。
回復には時間軸と回復力のある対象が必要になります。
このデメリットに対してどうすれば?
- 10〜20年の長期を前提にし途中での取り崩し予定がある部分は現金・短期債に分ける
- 目標が5年以内なら、値動きの小さい資産(債券比率や元本確保型を含む)も検討する
短期での利益は狙いにくい
ドルコスト平均法は時間をかけて平均購入単価を平準化する設計です。
したがって、「数ヶ月で大きく増やす」短期目的とは相性が悪いです。
また相場が右肩上がりの期間では後から買う分が高値になりやすく、同額の一括投資よりリターンが低くなる傾向があります。
“安全に見えるのに伸びが鈍い”と感じるのは、この特性によるものです。
積立NISAを途中でやめたらどうなる?売却・解約・非課税枠の最新ルール【2025年版】
例:3ヶ月で100→110→120と上がる局面。毎月1万円の積立は、後半ほど高い価格で買うため、初月に3万円を一括投資した場合より評価益が小さくなりやすいです。
これは“失敗”ではなく、平準化の副作用=上昇トレンドでの機会損失です。
このデメリットにはどうすれば?
- 安易に積立額を増減しすぎない(ルールがぶれると平均化の効果が弱まる)
- 「上昇がはっきりしているインデックス」を長期保有と決めた場合、初期一括+以後積立(ハイブリッド)も選択肢
なるほど~絶対に利益が出るとは限らないんだね!
あくまでも手法の一つだからね。
「損する」とはどういうことか?具体例で解説
「ドルコスト平均法は損する」と聞くと不安になりますが、実際には次のようなケースがあります。
一括投資と比べた場合の違い
ドルコスト平均法は一定額を分散して購入するため「高値掴みのリスク」を減らせる一方、相場がずっと上がり続ける場面では一括投資の方が有利になります。
なぜなら一括投資は最初の安い価格でまとめて買えるのに対し、積立は後半に進むほど高い値段で購入するからです。
例:資金30万円、基準価額が1,000円 → 1,200円 → 1,400円と上がり続けた場合
毎月1万円ずつ:後半は高い価格で買うため、平均取得単価は1,200円付近まで上昇
結果、一括投資の方が最終的な口数が多く、リターンも大きくなります。
一括投資:初月に1,000円で300口
相場が右肩上がりの場合の失敗例
私自身、2019年に毎月2万円を積立投資した経験があります。当時はコロナショックで一時的に下落したもののその後は株価が大きく回復しました。
もし2019年の初めに一括投資していたら積立よりも約1.5倍のリターンが得られていた計算になります。
このケースでは「積立が間違い」だったわけではありません。
ただドルコスト平均法は上昇トレンドでの伸びを最大化する仕組みではないことを、実体験を通じて理解できました。
つまり「安心して続けられる代わりに、強い上昇局面ではリターンが鈍る」点がデメリットになるのです。
シミュレーションで考える
仮に毎月1万円を5年間(60万円)積み立てるケースを考えましょう。
- 年平均で3%ずつ上がる相場
- 毎年の価格は緩やかに上昇
この場合、一括で最初に60万円を投資した方が、積立よりもリターンは大きくなる傾向があります。積立は途中の高値でも買い続けるため、平均購入単価が上がるからです。
一方、価格が上下しながら最終的に緩やかに上がるような相場では、積立が功を奏し「安い時期に多く買えた分」が効いて一括との差が縮まる、あるいは積立が勝ることもあります。
資産形成の基本:NISA特設ウェブサイト:金融庁
初心者が注意すべきポイント
積立額は無理のない範囲で設定する
ドルコスト平均法は「続けること」が前提です。
途中で家計が苦しくなって中断してしまうと、安い局面で買い増すチャンスを逃してしまいます。
目安としては「生活費の1〜2割以内」「余剰資金の範囲」で設定すると無理がありません。
積立NISAや投資信託は元本割れする?怖さを解消する考え方と体験談【初心者向け】
投資期間を短くしすぎない
積立の効果は時間をかけて平均購入単価をならすことにあります。3年程度では値動きに振り回される可能性が高く、10年以上のスパンを想定するのが安心です。
教育資金など期限が決まっている目的には向かないため、使うお金と投資するお金は分けて考えることが大切です。
投資対象の選び方
同じ積立でも手数料の高いファンドや値動きが極端なテーマ型商品を選ぶと積立効果が損なわれやすいです。
初心者はまず全世界株式やS&P500といった広く分散された低コストのインデックスファンドを選ぶのが無難です。
ドルコスト平均法と相性の良い制度
積立NISAとの組み合わせ
新NISAのつみたて投資枠は毎月一定額を自動で積み立てる仕組みなので、まさにドルコスト平均法をそのまま実践できる制度です。
毎月決まった金額を継続して投資することで高いときは少なく安いときは多く買う、というドルコスト平均法の特徴が自然に働きます。
ポイントは、まず家計に無理のない金額を決めて積立投資枠に低コストのインデックスファンド(全世界株式やS&P500など)を設定し、あとは自動積立に任せることです。
途中で「今は高いからやめよう」と判断を変えると平均化の効果が崩れてしまうので、積立額の見直しは年に一度程度にとどめるのが現実的です。
NISAは銀行?ネット証券?初心者が迷わない口座開設の選び方【2025年最新版】
iDeCoでの活用
iDeCoは拠出が毎月固定でドルコスト平均法が仕組みとして最初から組み込まれています。老後資金という長期目的に限定して無理のない額を設定します。
商品は低コストの株式インデックスを中心に据え、受給時期が近づくほど債券など安定資産の比率を段階的に高める“グライドパス”で値動きをならします。
節税メリットは大きいものの、60歳まで原則引き出せない点だけは最初に腹落ちさせておくと、途中で迷いが生まれません。
iDeCo(イデコ)のメリット・デメリット【2025年最新版】
まとめ|リスクを理解したうえで長期投資に活かそう
ドルコスト平均法は投資初心者にとって心強い仕組みですが、「必ず儲かる方法」ではありません。
- 相場の下落が続けば損することもある
- 上昇相場では一括投資に劣るケースもある
- 継続できる積立額と投資期間が大事
こうしたリスクを理解したうえで、積立NISAやiDeCoと組み合わせて長期投資に取り組むことで、より安心して資産形成につなげることができます。
投資に関する留意事項
本記事は、筆者の体験や一般的な情報に基づき執筆したものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任で行ってください。
記事内の数値・制度・サービス内容は執筆時点の情報に基づいており、将来変更される可能性があります。
最新情報は必ず金融庁・証券会社などの公的サイトをご確認ください。
当サイトは、リンク先の外部サイトの内容や成果について一切の責任を負いません。
👉 関連記事
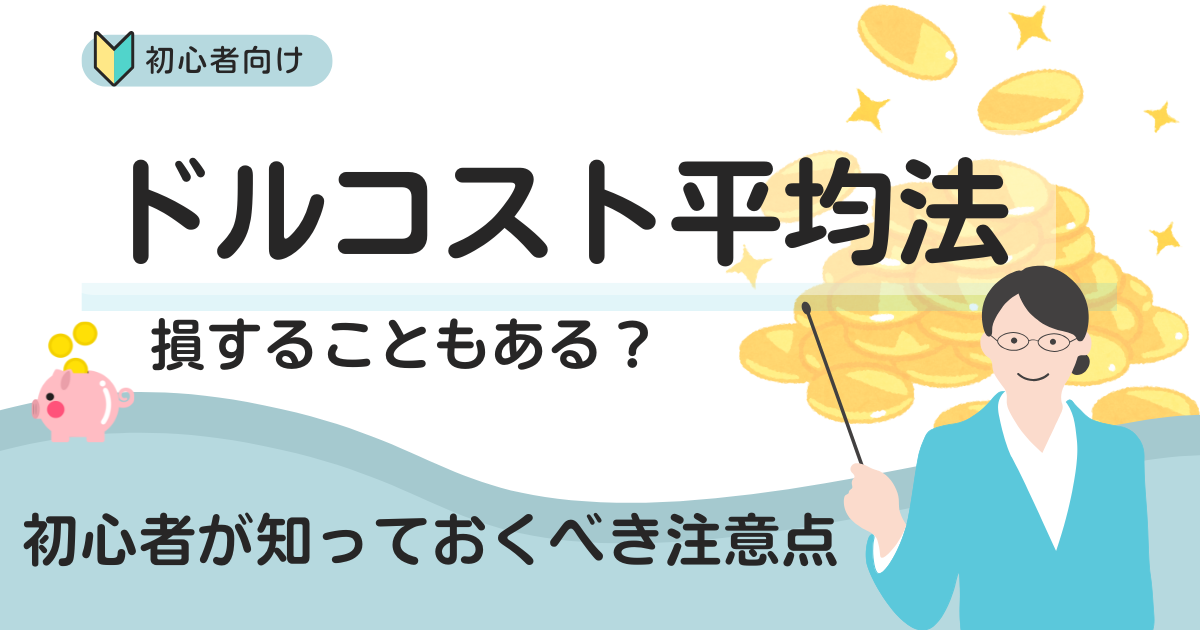


コメント