はじめに
最初に積立NISAを設定するとき、私は「積立日をいつにすればいいんだろう」と悩みました。
積立NISAを始めようと思ったけど…最初のつまづき
新NISAの制度を理解したあと、次にやることは「積立設定」です。
しかし多くの初心者がここで立ち止まります。
「積立日はいつにすればいいの?」
「みんなが同じ日に買うと、自分も高値掴みになるんじゃない?」
こんな疑問を持つ人は少なくありません。私も最初は月初・月末を避けるべきか迷いました。
実際に最初は、中途半端な日に設定したり、試行錯誤した経験があります。
本記事では、初心者がつまずきやすい「積立日」に焦点をあて、制度面からわかりやすく解説していきます。
記事を読み終えるころには、「どの日に設定しても大きな差はない」と安心できるはずです。
始め方の詳細は「積立NISAの始め方|初心者でも簡単にできるやり方【2025年最新版】」で解説しています。
新NISA、つみたて投資枠の基本を簡単におさらい
新NISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあります。
初心者がまず活用するのは、無期限で非課税で運用できる「つみたて投資枠」です。
生涯での非課税保有上限額は「つみたて」「成長」合わせて1800万円となっています。
年間上限は120万円、月あたりでは10万円まで投資可能です。
以下の表で整理しておきます。
| 区分 | 年間上限 | 主な対象商品 | 非課税期間 | 生涯投資枠 |
|---|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 金融庁指定の投資信託・ETF | 無期限 | 1,800万円 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 上場株式・投資信託など | 無期限 | 1,200万円※ |
※新NISAの生涯投資枠は合計1,800万円です。そのうち成長投資枠として使えるのは最大1,200万円までとなります。つみたて投資枠については、残りの枠を自由に振り分けて利用できます。
出典:金融庁「新しいNISA」
積立NISAは、指定した日付を基準に毎月自動で買付されます。では、その日付は何日にするのが良いのでしょうか。
何を買えばいいの?投資信託の選び方は「新NISAで買える投資信託の選び方」を参考にしてください。
積立日はいつにするのがいいの?
私自身は最初「月末はみんなが買うから値段が上がるのでは?」と心配して、わざと中旬に設定しました。ところが数年運用してみると、積立日による差はほとんどなく、むしろ「続けやすい日」にすることが大事だと実感しました。
月末・月初・給料日後など「続けやすい日」を軸に考える
積立NISAの積立日は「月末」「月初」「給料日のあと」など、生活のサイクルに合わせて設定して問題ありません。
たとえば給料日のあとに設定しておけば、証券口座の残高不足を防ぎやすいですし、クレカ積立にしておけば毎月自動的に処理されるため、意識せずに投資を続けられます。
積立投資は「長く続けること」が最大のメリットです。1回あたりの買値よりも、長期で平均購入単価を下げていくことが本質だからです。
積立日は“継続しやすい日”で選ぶのがコツなんだよ
じゃあ、特別に“得する日”っていうのはないんですね
こうした会話のとおり、特定の日を狙っても得することはありません。。むしろ自分にとって「毎月忘れずに続けられる日」を優先するのがおすすめです。
内部リンク:投資を続けるコツは【積立NISAのやめどきはいつ?やめ方の注意点】でも解説しています。
みんな同じ日だと損?
「月末はみんな買うから相場が上がり、高値掴みになるのでは?」と心配する人もいます。実際にネット上のQ&Aでもよく見かける疑問です。
しかし、結論から言えばその心配は不要です。理由は次のとおりです。
- 個人投資家の積立額は市場全体から見ればごくわずか
- 特定の日に多少の買い注文が集中しても、市場全体の価格を押し上げるほどの影響はない
- 過去のシミュレーションでも、積立日による長期リターンの差は統計的に僅少
つまり「月末だから損する」「月初だから得する」といった差は事実上ないのです。
この点については【ドルコスト平均法とは?初心者が誤解しやすいポイント】でも詳しく説明しています。
高値掴みにはならない理由
最初は「月末にみんなが積立するから、その日に価格が上がるのでは?」と不安でした。ですが実際に市場規模や過去の検証例を調べてみると、積立日による差はほとんど気にしなくてよいとわかりました。
個人の積立額は市場全体に対して極めて小さく価格影響は限定的
株式市場は毎日、数兆円規模の取引が行われています。例えば東京証券取引所の2024年の1日あたり売買代金は平均で約3兆円を超えています(出典:日本取引所グループ)。
一方、積立NISAで投資できるのは月10万円まで。仮に数十万人が同じ日に一斉に購入したとしても、市場全体から見れば誤差の範囲にすぎません。
つまり「月末だから高値掴みになる」といった懸念は現実的ではなく、個人投資家の積立注文が相場を押し上げることはないと考えてよいでしょう。
過去データ・検証例から読み取れる傾向:積立日による差は限定的
過去の市場データを使った複数の検証でも、積立日による大きな有利・不利は確認されていません。
例えば金融情報サイトの比較では、積立日を「月初・月中・月末」で分けて20年近くのシミュレーションを行ったところ、最も良い日と悪い日の差はわずか数%に収まるケースが大半でした(参考:Diamond ZAi)。
また、他の投資情報サイトでも「長期で見れば積立日による成績差は1〜2%程度」とする見解が紹介されています(参考:my-best)。
このように、日付による違いはあるとしてもごく僅かであり、長期運用においてはほとんど気にする必要はありません。むしろ「継続できる日付に設定すること」が最も大切です。
次は意外と知らない積立日、約定日、受渡日の整理してみましょう。
意外と知らない「積立日」「約定日」「受渡日」
最初は「積立日=買値が決まる日」と思い込み、明細の反映が翌日以降になる理由にかなり戸惑いました(どこで金額が確定するのか、理解に苦労しました)。
用語整理:積立日・約定日・受渡日の違いを一枚で把握
「積立日」は“自動で注文を出す日”。実際の買値が決まるのは「約定日」で、投資信託は約定日の基準価額が適用され、その価額の確定は翌営業日に判明するのが一般的です。楽天証券:基準価額が決定するタイミングは?
代金や受け取る口数の“決済”は「受渡日」に行われ、投信はファンドごとに日数が異なります。
株式は原則 T+2(約定の2営業日後に受渡)。東証は2019年からT+2を実施しています。
株式の場合は「約定日(取引が成立した日)」の2営業日後にお金と株が正式に受け渡しされます。これを「T+2」と呼びます。
- 「T」は取引日(Trade date)の略
- 「+2」は2営業日後に受渡が完了することを意味します
たとえば月曜日に株を買ったら、水曜日に代金が引き落とされて株が自分のものになる、というイメージです。東証では2019年からこの「T+2方式」が導入されています。
下の簡易表で流れを確認しましょう(例:平日注文/一般的なケース)。
| 商品 | 積立日(注文) | 約定日 | 受渡日 | 価格の決まり方 |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 5日 | 5日 or 6日 | 7〜9日 | 約定日の基準価額(確定は翌営業日に判明) |
| 国内株式 | 5日 | 5日 | 7日(T+2) | 板で即時に決定 |
“積立日=約定日”じゃない点がをまず覚えよう
買値は“約定日の基準価額”、覚えておきます!
よくある落とし穴:残高不足・入金タイミングずれ・他取引での資金拘束
つまずきやすいのが口座残高。投信は基準価額が翌営業日に確定するため、発注時に余裕資金がないと未約定・エラーの原因になります(証券会社の締切や前受金制の有無にも注意)。
また、株式や他の取引で受渡待ちの資金があると、その分が拘束され積立日に買えないことも。株式の受渡はT+2なので、売却代金を積立原資に充てる場合は2営業日後に入金される前提で日程を組みましょう。
対策はシンプルで、①給料日直後に入金→積立日の順に資金フローを固定、②投信は「基準価額確定が翌営業日」という性質を前提に最低限の余裕資金を残すこと。楽天証券の案内でも、基準価額は1日1回算出・夜間に更新されることが明示されています。楽天証券
残高不足で買えなかったトホホな失敗談
投資を始めた当初は「毎月きちんと積立できる」と思っていましたが、実際には証券口座の資金管理を甘く見ていて、ある月に積立ができなかったことがあります。
短期売買もしていたが故に起こったわが家の失敗
2022年の秋、私は個別株の短期売買を並行して行っていました。月5万円の積立NISAを設定していたのですが、ちょうど同じ時期に信用取引をしており、株式の売却代金が受渡日(T+2)の関係でまだ口座に反映されていませんでした。
結果、積立日に証券口座の残高が不足し、積立注文が未約定となってしまいました。幸い、翌営業日に繰り越されて購入はできましたが、もし資金移動を忘れていたら、1か月分の積立を丸ごと逃すところでした。
この経験から学んだのは、積立用の資金は売買資金と混ぜず、常に余裕を残しておくことの大切さです。生活費と同じように「積立専用口座」に先取りで入れておけば、こうしたミスは防げます。
経験から学んだ積立日の設定方法
この失敗以降、私は積立NISAを「クレカ積立」に切り替えました。クレジットカード決済なら、残高不足を気にする必要がなく、毎月自動的に決済されるからです。
例えばSBI証券では三井住友カード、楽天証券では楽天カードといったように、証券会社ごとに利用できるカードが決まっています。クレカ積立にはポイント還元のメリットもあるため、残高管理と合わせて一石二鳥です。
現在、多くの証券会社×カードのクレカ積立は上限が月10万円です。満額(つみたて投資枠の平均月額)までならクレカ積立だけで足りますが、上限やポイント条件は各社で異なるため、利用先の最新条件を確認してください。
FAQ(よくある質問)
積立日を決めるとき、多くの人が同じような疑問にぶつかります。ここでは代表的な質問を整理しました。私自身も最初は「途中で日付を変えると損するのでは?」と不安になったので、参考になれば幸いです。
Q:積立日を途中で変えると損しますか?/A:影響は軽微、継続性優先
積立日は途中で変更しても問題ありません。投資信託の基準価額は毎営業日変動するため、日を変えた瞬間に少し高い・安いといったことは起こります。
しかし、長期で毎月積立てていくと、その差は誤差レベルになります。むしろ「日付変更の手続きで積立が止まる」リスクの方が大きいため、気になるときは早めに修正して、安心して続けることを優先しましょう。
Q:土日・祝日が積立日の場合はどうなる?
金融機関は営業日ベースで動いているため、積立日が土日や祝日に重なった場合は翌営業日にずれます。
例えば「毎月1日」に設定していて、その日が日曜日なら「翌月曜(営業日)」が積立日扱いです。証券会社各社も公式サイトで同様に案内しています。安心して設定して大丈夫です。
Q:ボーナス月だけ増額設定はアリ?手数料や約定への影響
ボーナス月だけ積立額を増やす「増額設定」は、多くの証券会社で可能です。つみたてNISAの年間上限(120万円)の範囲内であれば、月ごとの金額を変えても問題ありません。
増額しても手数料が特別に高くなることはなく、通常の積立と同じルールで約定します。資金に余裕がある月は上手に活用しましょう。
Q:クレカ積立のポイントと決済日・引落日の関係
クレカ積立では、利用できるクレジットカードや還元率が証券会社ごとに異なります。
クレカ積立の主要3社比較(2025年10月時点)
| 証券会社 | 対応カード | 月上限 | 買付日/締切 | 引落日 | ポイント還元の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード | 10万円 | 7・8・9日/毎月10日締切 | 10日 or 26日 | 初年度0.5%、以降は条件次第 |
| 楽天証券 | 楽天カード | 10万円 | 1・8・12日/毎月12日締切 | 27日 | 種別・条件で変動 |
| auカブコム証券 | au PAYカード | 10万円 | 毎月1日/21日の4営業日前締切 | 10日 | 通常0.5%、ゴールド等は最大1% |
カード会社の締め日と引落日は、証券会社の積立日とは別に設定されています。たとえば「毎月1日に積立 → 翌月27日にクレカ引落」といった流れです。詳細は各社の公式資料を必ず確認してください。
まとめ
この記事を書きながら改めて「積立日は自分の生活に合った日を選ぶことが一番大事」だと学び直しました。制度や仕組みを理解するよりも、まずは無理なく続けられるかどうかが鍵です。
結論:積立日は「好きな日でOK」—有利不利の差は無視できる範囲
積立日は月初でも月末でも、給料日後でも大丈夫です。
- 個人の積立額は市場全体に比べて微々たるもの
- 過去の検証でも積立日によるリターン差はごくわずか
- 長期積立では「続けること」が最重要
つまり「月末だから損をする」といった心配は不要です。読者の疑問「高値掴みにならないのか?」には、データと制度の両面から「ならない」と答えられます。
入金→約定→受渡で無理なく続ける
積立投資では、資金フローを安定させることが失敗を防ぐポイントです。
- 入金タイミングを給料日直後に固定
- 「積立日 → 約定日 → 受渡日」の流れを把握
- クレカ積立や自動入金を活用して残高不足を防ぐ
この流れを理解しておけば、残高不足で買えなかったり、資金拘束に気づかないといったトラブルを避けられます。一度この段取りを決めれば、翌月からは手を動かさずに投資が回り、日付選びで悩む必要もなくなります。
「続く仕組みを作れば、積立は“考えない投資”になるんだ
日付で悩むより、生活に合った形で設定するのが正解ですね!
投資に関する免責事項
本記事の内容は、筆者自身の体験や公的機関・証券会社が公開している資料をもとにまとめた一般的な情報提供です。特定の金融商品や投資手法を推奨するものではありません。
投資には元本割れなどのリスクがあり、運用成果は保証されません。実際に投資を行う際は、必ず最新の制度内容や証券会社の取引ルールを確認のうえ、ご自身の判断と責任で行ってください。
出典:
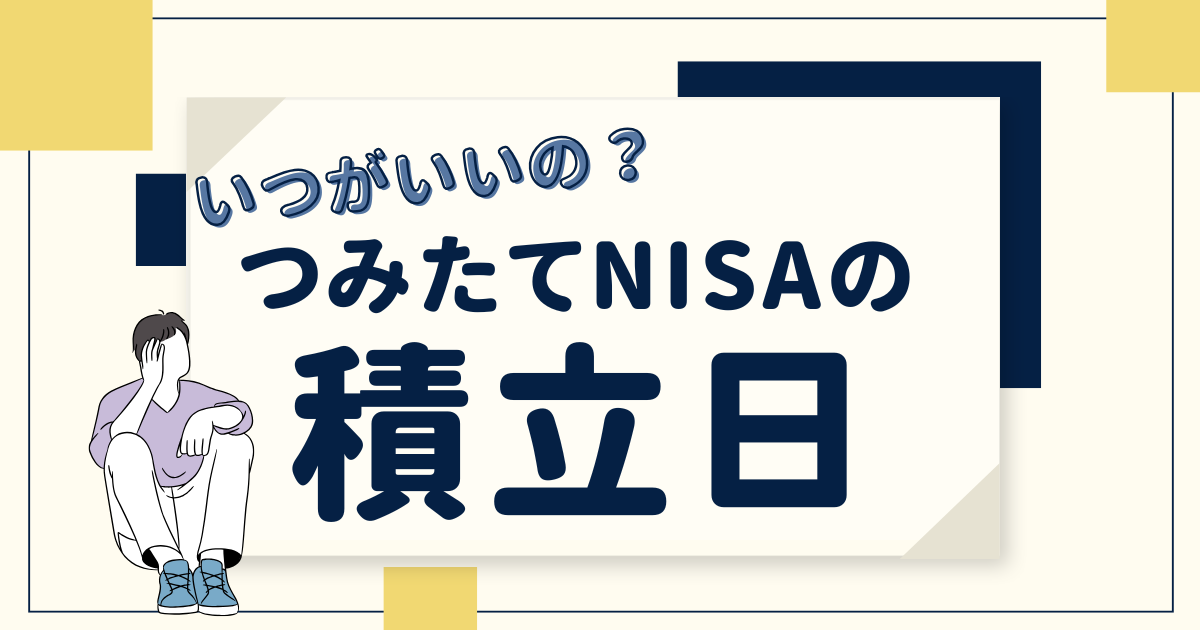
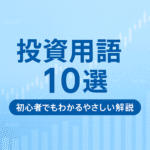
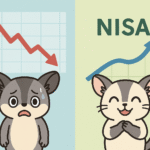
コメント